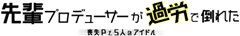
プロデューサールームの中はおおかた片付け終えた。
改めて眺めてみれば、俺には広すぎる、過大な部屋とデスクだったと思う。
デスクのモニターの横には、茜たちを撮った写真をスライドショーで流し続けるフォトフレーム。俺はそれをしばし見つめてから、パソコンのメールソフトを立ち上げる。下書きボックスに保存されたメールを開いた。すでに文面は完成している。あとは宛先を入力して送信するのみ。
俺は茜、比奈、春菜、裕美、ほたるのアドレスを入力して、ひとつ呼吸をしてから送信ボタンを押す。あまりにもあっけなく、メールは送信された。
サマーフェスが終わってから心に決めていたことがある。
俺はあいつら五人をできる限り高いところまで連れて行く。そのためなら手段を選ばない。
プロダクションでもトップクラスの敏腕プロデューサーである先輩が戻ってきたいま、とるべき選択肢はひとつ。
俺が居なくなること。そうすれば、もとの通りに先輩が茜達五人をプロデュースすることになる。
それがいちばん、あいつらが輝ける確率を高くする。なぜなら、先輩は敏腕だから。
なにもおかしなことじゃない。
先輩プロデューサーが過労で倒れた。
それを俺が引き継いだ時から、この結果になることは決まっていた。
俺はパソコンとフォトフレームの電源を落とす。
鞄にフォトフレームをしまうかどうか一瞬悩んで、結局置いていくことにして、卓上に伏せて置いた。
財布と手帳以外に大して荷物も入っていないビジネスバッグを乱暴に担いで、俺はプロデューサールームの照明を落とすと、部屋を後にした。
そんなに複雑な計画ではない。
先輩の復帰に合わせ、俺の親が急病になったことにして、介護のために休暇をとる。そのあいだのユニットの対応を一時的なものとして先輩に預ける。もともと、先輩が立てたスケジュールに俺が肉付けしたのだから、先輩が担当するのがいちばんスムーズだ。
あとはそのままずるずる休暇を引き延ばして、フェードアウトするだけだ。俺が必要なくなった頃に正式な退職願をだして、借家の荷物の引き上げをすればいい。
五人に送ったメールも、急に実家に戻る必要が出たから、不在のあいだの対応をもともとのプロデューサーである先輩に頼んでいるという内容だ。同じ内容で上司と先輩にも連絡済み。
実家の住所は美城プロダクションの誰にも知らせていないから、追跡することもできない。俺のプロデューサーとしての経歴は、こうしてひっそりと幕を閉じる。
「プロデューサー!」
ロビーを歩いていると、背中に声がかかった。
「……比奈か」
俺は後ろを振り向く。ジャージ姿の比奈がこちらに走ってきていた。
比奈にレッスンの予定はなかったはずだ。というか、比奈にレッスンの予定が入っていない日を選んだ。ほかの四人は日中、学校があるから、プロダクションから出ていく俺と鉢合わせすることはない。
比奈にレッスンの予定がないにもかかわらずここにいるということは、自主的なレッスンか。
タイミングが悪い。
「メール、見たっス。……行っちゃうんスか」
比奈は真剣な眼をして俺の前に立つ。
「あー、まぁ、ちょっと、メールの通りでな、親が――」
「どのくらいで帰ってくるっスか?」
比奈は俺の言葉を遮るように言う。
「病状見てからだな」
「……戻ってこないつもりっスね?」
「……いや、そんなつもりじゃ……」
「あのとき」比奈はうつむく。「サマーフェスのとき、アタシたちのユニットのこと、ちゃんと責任取ってくれるって言ってたじゃないっスか、あれは……嘘だったんスか?」
比奈の声は、すこし震えているように聞こえた。
「そんなことはないさ。責任を取る」
「じゃあ」
「大丈夫だ。先輩は敏腕だからな。必ずお前たちを輝かせてくれる」
「そうじゃないっス!」比奈はうつむいたまま若干語勢を強め、首を横に振る。「そうじゃないっスよプロデューサー……プロデューサーは、それでいいんスか……?」
「……お前たちが活躍するのがいちばんだよ」
「茜ちゃんも春菜ちゃんも裕美ちゃんもほたるちゃんも、プロデューサーは、置いていっちゃうんスか」
「……」
「そんなの、責任取るって言わないっス……このままじゃアタシ、ほんとうに共犯者になっちゃうっスよ……みんなになんて説明したらいいか」
「……」
「お休みから戻ってくる人が敏腕だから任せるって、プロデューサーはアタシたちと最後までやりたいと思ってはくれないんスか」
「……俺は、お前たちが高いところまで行けるほうを選ぶ」
「ほんとに、そう思ってるんスか」
「……ああ」
「……」
「お前たちなら……お前たちと先輩ならできるって確信してるよ」
「アタシ、まだあのとき借りた五千円返してないっス」
「ああ、あれな」思い出して、俺は笑う。スカウトのときの買い出しで立て替えていた五千円だ。「……いいよ、出世祝いの先払いだ」
「……」
比奈はうつむいたまま、小さく肩を震わせていた。
俺は黙って、比奈に背を向けて、歩き出す。
「プロデューサーは、嘘をついてるっス」
俺の背中に向かって比奈が低い声で言う。俺は足を止めた。
「言ったでしょう。アタシ、マンガ描いてるくらいっスから、人間観察力は高いんスよ……プロデューサー、アタシと話してるあいだ、一回もアタシのこと見てないっス」
最後のほうは、ほとんどかすれ声だった。
これ以上はだめだと俺は思った。
「比奈、お前たちが思っている以上に芸能界は厳しい。だから一番近道を行け。それが、お前たちにとって一番いいことなんだ。……またな。比奈」
俺は比奈に背中を向けたまま言い、歩き出した。比奈はもう、俺を引き留めなかった。
「……と、ここだな」
窓側に取った新幹線の指定席。荷物を棚に乗せて、俺は席につく。平日の昼間、乗客はまばらだった。
想像していたよりも、実感がないと思っていた。もうすこし気分が沈むかと思っていた。自分で自分の感情に蓋をしているのかもしれないと思う。
もともと、感情に蓋をするのは得意だったしな、と心中で自分を皮肉った。
座席のリクライニングシートを少し倒す。長い息をついた。
俺としては、少なくとも合理的な選択であったと思う。
茜、比奈、春菜、裕美、ほたるの五人が活躍するためなら、俺一人の感情は抑制する。そうして、俺よりも優れたプロデューサーに渡す。それが、俺ができる最良のプロデュースだ。
発車ベルが鳴って、ドアが閉まった。新幹線がゆっくりと走り出す。
売店で買っておいた缶ビールのプルタブを起こす。小気味いい音が響いた。
ビールを喉に流し込む。
こんなに味のしないビールを飲んだのははじめてだった。
茜は自室のベッドの上で、スマートフォンの画面を見つめて眉間にしわを寄せていた。
プロデューサーから、実家の都合でしばらくお休みするという連絡をもらってからまる二日間、ユニットのメンバーのあいだではグループメッセージのやり取りが続いていた。
最初、みんな一様にプロデューサーのことを心配していた。茜も同じ気持ちだった。
茜にとってすこし嬉しかったのは、ほたるがプロデューサーに起こったことを自分の不幸のせいだと落ち込んだりすることがなかったことだった。プロデューサーのいないあいだ、頑張って活動を続けようと最初にみんなをはげましてくれたのはほたるで、ほたるがそう言うならとみんなが奮起した。
いいユニットに参加することができたと、茜は素直に嬉しく感じていた。
それから話題は、プロデューサーが不在の間を引き継ぐことになっているという、新しいプロデューサー――今までのプロデューサーにとっての先輩プロデューサー――のことに移っていった。
『これまでも数々のユニットをプロデュースしてきたすごく実力のあるプロデューサーらしいっスから、お任せしちゃって大丈夫だと思うっス。病み上がりなのはちょっと心配っスけど』
比奈から茜を含む四人へのグループメッセージが届く。
『新しいプロデューサーからのメールには心配しないでいいって書いてありましたけど、やっぱり最初のほうは私たちもあまり負担をかけないようにしたほうがいいですよね』
すぐに、春菜からのメッセージが返ってくる。
茜は仰向けになったまま、むー、と唸った。
「どうしてまだ私にだけ、その新しいプロデューサーさんからのメールが、こないんでしょう……」
茜はスマートフォンの画面を見ながらつぶやいた。
茜以外の四人には、すでに先輩プロデューサーからの挨拶と、引継をしたこと、顔合わせの日程を伝えるメールが届いていた。
ユニットのメンバーでメッセージのやり取りをしているあいだに、茜にだけその連絡がきていないことがわかった。
四人は茜に、メールアドレスを間違えたんじゃないのかとか、なにかのエラーじゃないか、送り忘れなど可能性をあげて、気にする事はないと励ましてくれていた。茜はそれに同意をしつつ、どこかで不安がぬぐえずにいた。
もともと、茜たち五人のユニットは、これから引き継ぐ先輩プロデューサーが企画したもので、先輩プロデューサーが過労で倒れたことによって、今は実家に戻っているプロデューサーが急遽担当することになったと聞かされていた。当初のメンバーは、春菜、裕美、ほたると、スカウト予定だった比奈、それに当時未定だった新メンバーを加えての五人で、その新メンバーが茜ということだった。
つまり、茜だけは、これから引き継ぐ先輩プロデューサーが想定していなかったメンバーということになる。
そのことを思い出したときから、茜の心に不安が生まれた。
もし――もし、先輩プロデューサーが、茜のことを気に入らなかったのだとしたら。詳しいことは茜には想像も及ばなかったが、もともとのコンセプトや、想定していたユニットのカラーが先輩プロデューサーの意向に合わなくて、それで連絡がもらえていないのだとしたら。
茜だけ、みんなと一緒にアイドルを続けることが、できなくなるかもしれない――
そう考えて、茜は自分の胸のあたりに手を当てた。不安で鼓動が早くなっている。
「なんだか、不思議ですね」
茜はぼんやりと天井を見つめて呟いた。
数か月前まで、アイドルになるなんて考えたこともなかった。
人前に出て歌ったり踊ったりするなんて、やってみたいかどうかすら考えたこともなかった。
それが、いつのまにか、スカウトを受けて、アイドルとして活動することになって、レッスンや仕事を繰り返し、ライブに出て、今はこれからもアイドルをやりたいと思っている。
「私、こんなにアイドルやりたかったんですね……」
皮肉にも、アイドルを続ける道が危ういかもしれないという想像を通して、茜はそれを実感していた。
一人の時に、一度考えが沈みだすと、悪いほうへ、悪いほうへとずぶずぶ引きずられていく。みんなと一緒にユニットができなくなるかもしれない。そもそもアイドル自体続けられなくなるかもしれない。いや、本当は自分はアイドルなんかじゃなくて、アイドルであると勘違いしていただけなのかもしれない――
茜はスマートフォンを置いてベッドから体を起こし、悪い想像を追い出そうと頭をぶんぶん左右に振った。それから、気合を入れようと、両手で自分の頬を軽く叩く。
「悪いように考えちゃいけませんね! しっかりしましょう! ボンバー!」
茜は右手を振り上げ自分を鼓舞して、練習中のユニット曲を口ずさみながら、振りを確認する。
しかしそれは長くは続かず、茜は部屋の真ん中に立ったまま肩を落とした。
「プロデューサー、早く戻ってきてください……」
茜はスマートフォンのメールボックスを開いた。
実家に帰ったプロデューサーからユニットのメンバーに届いた、最後のメールを開く。もう何度読み返したかわからなかった。
メールには一時的に実家に帰ると書かれている。
だけど、茜には、なぜだかプロデューサーがもう戻ってこないんじゃないかという不安があった。
スマートフォンがメッセージの着信を振動で知らせる。比奈からだった。
『まー、明日は新しいプロデューサーとの顔合わせっス、色々不安っスけど、みんなしっかり打ち合わせしてこれからに臨みましょう』
茜はその文面を見て、そのとおりだと思う一方で、比奈が少しドライなようにも感じた。けれども、すぐにそれは茜の不安がそう思わせるのだと考え直した。
茜はもう一度、歯を食いしばって、さっきより強く両側の頬をはたいた。
「それじゃー、いろいろバタバタして悪いんだけど、とりあえずユニットのプロデュースはアイツが戻ってくるまでのあいだボクが引き継ぐから、みんなよろしくね」
すこし軽い感じの声で、先輩プロデューサーはそう挨拶した。
プロデューサールームに集まっていた比奈、春菜、裕美、ほたるの四人はそれぞれに「よろしくおねがいします」と言いながら頭を下げた。茜は学校ですこし遅れるという連絡が入っていて、まだ到着していない。
比奈はプロデューサールームを見渡した。もともと、実家に帰ったプロデューサーの私物は多くはなかったが、部屋の中は綺麗に片付いていて、プロデューサーがここにいた痕跡が消えてしまっている。
「手口、鮮やかっスね」
比奈は誰にも聞こえないようにつぶやいて、溜息をついた。
「病み上がりってのもあるんだけど、入院してるあいだは仕事のことはシャットアウトしろってんで、この数か月間のプロダクションのこともこのユニットのこともぜんぜん教えてもらってなくってね。みんなにはちょっと迷惑かけるけど、できるだけ早く追いつくよ。アイツはボクがもともと立ててたスケジュールにだいたい沿ったかたちで進めてくれてたみたいだから、ちゃんと把握するまでそんなに時間はもらわないで済むと思う。改めて、メンバーは……」
先輩プロデューサーは四人を見渡す。
「っ、あの、プロデューサー」
比奈は先輩プロデューサーのことを『プロデューサー』と呼ぶことに若干の違和感を覚えながら、片手をあげる。
「まだ、茜ちゃんが到着してないっス」
先輩プロデューサーは笑顔で頷いた。
「荒木比奈さんだよね。参加してくれてありがとう。アイツ、ちゃんとスカウトにも行ってくれたんだな。ほんとはボクがスカウトにいくはずだったんだけど、倒れちゃったからさ。ごめんねー」
「あ、その……」
比奈はいろいろな想いをいっぺんに飲みこんだ。
比奈にとっては、目の前にいる人物は、本来書類選考で落選になっていたはずの比奈に魅力を見出し拾い上げた人物である。しかし同時に、この人物が戻ってきたことによって、比奈を実際にスカウトしに来た人物は会社を去ることを決めた。
どちらも比奈の人生を左右した大切な人物。もし先輩プロデューサーが戻らなければ、という想像が不謹慎だということも理解している。比奈は自分の気持ちに折り合いがつけられないまま、口を閉じた。
「それで……」先輩プロデューサーが困ったような顔で頭を掻く。「その、いま言ってた茜って子なんだけど……それ、誰なのかな?」
「えっ?」春菜が驚きの声をあげる。「誰って、日野茜ちゃんですよ、このユニットのメンバーの……ね?」
春菜はほかの三人のほうを見る。比奈、裕美、ほたるはそれぞれ春菜に頷いて、先輩プロデューサーを見る。
「うーん、まだ全部資料観れたわけじゃないし、茜って子の名前は報告書にちょいちょい出てくるんだけど……」先輩プロデューサーは腕組をした。「日野茜って名前の子、そもそも美城プロダクションにはいないんだよね」
先輩プロデューサーの言葉を理解できず、全員が固まる。
「ちょっと、それって、どういうこと!?」
直後に、裕美が大きな声をあげた。
茜は美城プロダクションの廊下を早歩きで進んでいた。学校の授業が終わり、いくつかの用事を終えてから到着したので、集合時刻に少し遅れてしまっている。
茜の胸にはずっと不安が残ったままだった。結局、先輩プロデューサーからの連絡はないまま。今日の顔合わせも、比奈から時間と場所を教えてもらっている。
それでも、顔合わせの場、プロデューサールームに行けば、大切な仲間たち、ユニットのメンバーがいる。だから、大丈夫。茜は自分にそう言い聞かせていた。
廊下の角を曲がると、プロデューサールームの扉が見えた。茜は入館証のストラップを持った右手をぎゅっと握る。何度も訪れたプロデューサールーム。茜をスカウトしてくれた人は、いまはあの部屋には、いない。
扉の前に立って、茜は胸に手を置いて、呼吸を整える。それから、右手をドアノブに伸ばした。
そのときだった。
「ちょっと、それって、どういうこと!?」
部屋の中から裕美の大きな声が聞こえてきた。
茜はドアノブに手をかけたまま、その場に固まる。
「えーと、だから……」
茜の知らない人の声が聞こえた。
おそらく、この声の持ち主が先輩プロデューサーなのだろうと茜は想像する。
茜はドアの内側に聞き耳を立てた。
「その日野茜って子は、プロダクションの所属アイドルのデータベースには登録されていないんだよ。美城プロダクションには、日野茜って名前のアイドルは、在籍していない」
「――っ!」
茜は息を呑んだ。心臓を潰されたような気がした。呑んだ息が吐きだせない。身体が震えているような気がした。心のなかに残っていた不安が一気に広がって、頭から足の先まで真っ黒に覆いつくす。
茜はドアノブを掴んでいた右手を、そろそろと離した。カチャ、とごく小さな音がする。
その音を立ててしまったことに茜は怯えた。
次の瞬間には、茜はその場から逃げ出していた。手から入館証のストラップが滑り落ちる。
茜は入館証を落としたことに気づいたが、戻ることはしなかった。
なにが起こっているのかわからなかった。
茜はただただ恐怖にとらわれ、廊下の角を曲がり、階段を駆け下りて美城プロダクションを飛び出していた。
「……なにか、音がした気がするっス。茜ちゃんでしょうか」
比奈はプロデューサールームの扉を開けて、廊下の左右を眺めた。
誰かが角を曲がって、去っていくのが見えた。
顔も体の大部分も見えなかったが、一瞬だけ目に映った足と革靴から、比奈はそれが茜だと予想した。
「茜ちゃん!」
比奈は部屋から飛び出し、小走りに廊下の角まで向かう。だが、そこにはもう人の姿はなかった。
比奈は首を傾げた。見間違いだったのかもしれないと思い、プロデューサールームに戻ろうとし――足元に、なにかが落ちていることに気づく。入館証だった。そこには確かに、日野茜と元気な文字で書かれている。
「……茜ちゃん……!」
比奈はそれを拾い上げると、プロデューサールームに戻った。話の途中で部屋から出て、また戻ってきた比奈を、春菜、裕美、ほたる、先輩プロデューサーの四人が不思議そうな顔で迎える。
「……茜ちゃんの入館証、そこに落ちてたっス。アタシたちの話をドアのところで聴いて、登録されてないって知ったとしたら……驚いて、いなくなっちゃったのかもしれないっス」
「そんな……」
ほたるが青ざめる。
「追いかけたほうがいいんじゃないかな」
裕美が言うが、先輩プロデューサーが一歩前に出た。
「ちょっと、待って……それ、見せてもらっていいかな」
比奈はうなづくと、入館証を手渡した。
「これは……」先輩プロデューサーは首をかしげる。「アルバイト証?」
「はぁ、はぁ、はぁっ!」
茜は走り続けていた。
美城プロダクションを飛び出して、大通りを一キロ近く疾走していた。
夕方の大通りは人も多く、ぶつからないように気をつけなければいけなかった。
それでも走り続けた。茜は怖いと思っていた。いま走るのをやめたら、そのまま押しつぶされてしまう。
先輩プロデューサーには自分のことを認めてもらえなかったのかもしれない。
そもそも、自分はユニットのコンセプトに合っていなかったのかもしれない。
もしかすると、自分はアイドルだと思い込んでいただけったのかもしれない。
ずっとずっと、自分の勘違い、思い上がりだったのかもしれない。
恐怖に呑まれて、茜の頭の中をたくさんの考えがぐるぐる巡っていった。
走りながら、茜は驚いていた。思った以上に、疲労を訴えてこない自分自身の身体に。
こんなに長く、早いスピードで走り続けているのに、まだ余裕がある。
たくさんレッスンをして、体力がついたからだ。――アイドルをするために。
体育会系の茜にとって、基礎体力が向上することはうれしいことのはずなのに、今はそれさえも茜の心を黒く塗りつぶそうとするものとして襲い掛かってくる。
「あっ!」
瞬間、雑念にとらわれた茜の足がもつれ、茜はアスファルトの歩道に転んだ。
膝と右の肩を地面にぶつける。通学鞄が転がっていった。
「う、う……!」
茜は痛みを感じながら、身体が傷ついていないか心配した。活発によく動く茜は、いつもプロデューサーから言われていた。顔はもちろん、肌が見えるところに傷をつけないように気をつけろと。
目立った傷がついていないことにほっとして、それからすぐに、もうその心配に意味がないかもしれないことを思い出す。
「ううっ……」
茜の視界がにじんだ。
それでも茜は立ち上がる。腕で両目を乱暴にぬぐって、大股で地面を歩いて転がった鞄を拾い、また走り出す。
止まってしまったら、なにかに飲みこまれてしまうと思っていた。
それから茜はさらに走り続け、河川敷までたどり着いていた。プロデューサーと出会い、スカウトを受けた河川敷に。秋の日は早く、河川敷は夕日を受けてオレンジに染まっていた。
ついに走り続ける体力も尽き、茜はスピードを落とす。
エネルギーを使い果たしたのと一緒に、茜の中の暗い考えもどこかに霧散していた。
とぼとぼと芝生の上を歩きながら、茜は涙をこぼして自分を笑った。
「あはは、逃げて、きて、しまいました」
茜は肩で息をしながら、今度は、どうして逃げてしまったんだろうと不思議に思っていた。
ユニットのみんなと出会ってから数か月は、ドキドキとワクワクの連続だった。なにもかもがはじめて体験することばかりで、毎日が輝いていた。
数か月のあいだに、みんなはどんどん強く、かっこよく、きれいに、可愛くなっていった。比奈も、春菜も、裕美も、ほたるも。……プロデューサーも、最初に会ったときよりも頼れるようになったと思う。
自分はどうだったろうかと、茜は考えた。考えて、涙がこぼれた。
自分には強さが足りなかったから、逃げ出してしまったんだ。
「……もっと、強くならなくちゃいけなかったですね」
茜はお気に入りの真っ赤なポロシャツの胸元をぎゅっと握って、はぁっと熱い息を吐いた。
強くなりたいと思った。けれど、ほんの少し、そう願うのが遅かった。
プロデューサーにスカウトしてもらって、こんなにアイドルをやりたいと思っているのに、目の前に、その道はもうなくなってしまっている。
どうしてこんなふうに思うようになったのか、茜自身にとっても、不思議だった。
「アイドル、もっと、やりたかったです……」
茜はそう口に出して、ついに歩みを止める。
それから空を見て、大粒の涙をぼろぼろ流した。
「うわあああああああああああああああああん!」
茜の大きな泣き声は、秋の空へと吸い込まれて行った。
・・・END