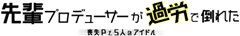
コントロールルームとレコーディングブースとを隔てるガラス窓の向こう、ブースの中にいる関裕美の表情は明らかに曇っていた。
となりにいるディレクターがこちらを気に掛けるような目線を送ってくる。
ブースの中の荒木比奈がさっき送ってきた視点も、裕美のことを伝えようと思ったからだろう。
さて、どうしたものか。
俺は小さく唸った。
一時間程度前。
「それじゃ、今日はよろしくちゃーん、唯と気楽におしゃべりしてくれればいいからねー」
大槻唯はそう言ってひらひらと手を振った。
「よろしくおねがいします!」
茜たち五人の声が重なる。
今日は五人そろってのラジオ出演だった。複合商業ビルのレコード店内に設置されたFM局のスタジオで、大槻唯がパーソナリティーを務めるラジオ番組でユニット活動の告知を行うことになっている。
収録前の最終打ち合わせを終えて、あとは放送開始時間を待つのみとなっていた。
茜と比奈は初めて訪れた収録スタジオに興味津々だ。
「私、初めてスタジオに入りました! こんなふうになってたんですね!」
「FM局、外からみたことはあっても、内側に入るのはさすがに経験ないっスね……見られながらの収録……緊張するっス」
比奈はスタジオと店舗を隔てる窓を眺めて言った。窓にはまだカーテンがかけられている。
収録スタジオには大きなデスクがあり、出演者はデスクを囲むようにして着席する。店舗内からは窓を通してスタジオ収録の様子を観覧することができるようになっていた。
「公開収録、だったんだ……」
すこし不安そうな声をあげたのは関裕美だった。
「資料にはたしか、そう書いてあったと思います」
ほたるが返事をした。裕美を気遣うような目で見ている。
「そっか。見落としてたかな、私」
「あとでこの窓の向こう、お客さんでいっぱいになるよー、土曜のお昼だしねー」唯が言う。「とりま、打ち合わせはこんなもんっしょ。いーよね、ディレクターちゃん?」
唯が尋ねると、番組ディレクターが頷いて一歩前に出る。
「十分前にはスタジオ入ってください。みなさん初めてのかたもいるみたいで、緊張すると思いますけど、唯に任せとけば心配ありませんので、気楽におしゃべりする感じで楽しんでください」
「じゃ、控室でリラックスしててくれ」
俺は五人に退室を促す。五人はぞろぞろとスタジオから出て行った。
スタジオの扉が閉まり、俺はディレクターに向きなおる。
「今日はよろしくお願いします。大所帯でみなさん大変じゃないかと」
「そこは唯が捌くので心配ないと思います。デキるパーソナリティーですよ」
「へっへー、まかせてー!」
唯はにぱっと笑う。
大槻唯、美城プロダクションの注目株。圧倒的なトークスキルで、どんなタイプの人間を相手にしても物おじせず、相手と自分をきっちり立たせて場をまとめることができる。
本人の軽い物言いと外見では想像しがたいほどの天性の才能を秘めたアイドルだ。
「心強いです」
俺は正直に言う。ユニットとしての活動を開始しているとはいえ、茜と比奈はラジオ収録そのものが初めてだ。実力のあるパーソナリティーに導かれて場数を踏めるなら願ってもない機会だ。
「PA担当さんに……おそらく茜は興奮すると、さっきの機材チェックのときよりも声がかなりデカくなるんで、それだけ先に伝えさせてもらって」
「はは、日野さんのマイクだけちょっとレベル落としてるって言ってましたよ」
ディレクターはそう言ってコントロールルームでミキサー卓の席についているPA担当を見た。
そのとき、スタジオの扉が開く。
入ってきたのは裕美だった。緊張した表情をしている。
「どうした?」
俺は裕美に声をかけた。
「スタジオの様子、もうすこし見ておきたくて」
俺はディレクターのほうを見る。ディレクターが頷いたので、了承と見なした。
「……窓、大きいね。ちょっとびっくり。お客さん、いっぱい来るのかな」
「普段はどうです?」
俺が尋ねると、唯が裕美のとなりに歩いてくる。
「けっこー来るよ? 時間がいいってのもあるけど、二十人くらい? すっごいゲストのときは、お店いっぱいなっちゃって大変だったよねーディレクターちゃん?」
「そうだなぁ……、それはさすがに大御所だったんで特殊ですけど、唯のファンとかも来るんで、空っぽってことはないっすよ、安心してください」
ディレクターはそう言って笑った。
俺は裕美のほうを見る。裕美は集客が少ないことを気にしているのではない。おそらくは逆だ。
裕美は、ギャラリーに見られることに不安を抱いているんだ。
裕美と接していて分かったことがいくつかある。最も大きなものは実力が高いということだ。裕美のレッスンへの取り組みは人一倍真面目だ。ダンス、ボーカル、ヴィジュアルとも、努力に裏打ちされた裕美のパフォーマンスは安定している。
一方で、裕美は裕美自身が単独で見られるような場面で精神的に弱い。ライブや今日のラジオの収録のように、人に見られながら話す場面があるとき。裕美一人が注目を浴びるような場面で、裕美は目に見えて不安そうにする。
つまり、自分に自信が持てていないのだ。
実力はあるのだから気にする必要はないのだが、こればかりは本人の心の問題だ。本人が乗り越える以外に解決策がない。
「特殊な環境だよな。こっちの声は相手に伝わるけど、窓の向こうの声はこっちには聞こえないって」
俺は裕美に話しかける。裕美は胸の前でぎゅっと拳を握り締めていた。眉間に力が入っている。裕美の不安のサインだ。
さてどうするか、と考えていると、俺よりも先に唯が裕美の前に出た。
「なーんか、不安そうじゃん?」
唯は裕美の眉間をつん、と指で軽く押す。
「楽しも楽しもー、力入ってたら、かわいー顔が台無しだよー?」
そう言って、唯は裕美の目を覗き込むように見つめた。
「あ……」
裕美は小さく声をあげて、ようやく、眉間に入っていた力を抜いた。
「うん! そっちのほうがいいっしょ?」
唯は裕美の肩をぽんぽんと叩く。
「……顔、こわばってたね。ありがと」
裕美が微笑んだ。
「キンチョーしてる? だいじょーぶだよ、これ、唯のラジオだから。どーんとぶつかってこーい!」
唯はそうして笑ったが、ほんの一瞬、ぎらりとした強い表情を見せた。
それで、俺は直感する。大槻唯。本人が意識しているかどうかは知らないが、おそらくは今よりもずっと高いところを見据えている。
ラジオの看板番組を持つことだって立派なことだ。だが、唯はそれだけで満足していない。だから、こんなにも余裕で、裕美を受け入れることができる。唯にとってはいまの位置は、当然通り過ぎるべき過程のひとつにすぎないのだ。
それなら――、と俺は思う。唯がそう言うのなら、裕美には、大いにぶつかってきてもらおう。
俺は引っ込むことにし、裕美と唯を残してコントロールルームへ下がる。
入れ替わりに、茜たち四人がレコーディングブースへと入っていった。
スタジオ内の緊張感がにわかに高まる。
ほどなくして、オンエアの時間が訪れた。
ここからは、俺は見守っているしかできない。けれど、不思議と俺は不安には思わなかった。先輩が選んだアイドルたちだということもあるし、何より、裕美も含めて、このユニットは、そんなに弱くはないと確信していた。
「……ってなわけで、今日のゲストは以上の五人のみなさんでお送りするよー。てゆーか、ウケるよねー、ユニットの名前、まだ未定なんでしょ? ゆいもユニット活動したことあるけど、フツー名前決めてから活動じゃん?」
「それはいろいろあったんですよ。ね、茜ちゃん?」
春菜が茜に振る。
「そうですっ!」ブースの中にも関わらず茜は立ち上がり、身を乗り出す。「いろいろ! あったんです!」
……一秒沈黙。
「って、それ説明しないと意味ないっしょー!」唯がけらけら笑う。「ま、アイドルにヒミツはつきものだよねーってことで! ユニット名は気になるトコだけどー、じゃーさっそく、そんな茜ちゃんから行ってみよーか、じゃじゃーん!」
効果音が入る。コーナーの合図だ。
「はいっ! ゲストのアガる曲を教えてもらって、それかけちゃお、みんなで聴いちゃおってコーナーだよー。じゃあ茜ちゃん、おしえておしえてー?」
唯は言いながら、左手で茜の手元の資料を示してウインクする。資料には進行に問題がないように、あらかじめ話す予定の内容を箇条書きにしてある。
俺はコントロールルームに置かれているモニターを見た。モニターにはレコード店内の様子が映されている。公開放送のブースには、人だかりができ始めていた。
「はいっ!」
茜は資料を両手で持って立ち上がる。
「ちょっ、待って待ってぇ!」唯も椅子の音を響かせて立ち上がる。「茜ちゃん立たなくていいし! ゆいのラジオで初めてだよ、立ったの! それじゃ授業で朗読するヒトみたいだよ、ちょーウケるね! いいね、そのままやっちゃって!」
「はいっ! 私はよく河川敷で走り込みをしているんですけれど、そのときにいつも口ずさんでいる曲を紹介します! お笑いタレントさんの歌うすこし古い曲なんですけど、とっても前向きな詩で、すっごく元気が出るんですよ! みなさんもぜひ、聴いて元気になってください!」
「オッケー、じゃあ茜ちゃんのアガる曲、行ってみましょー、どぞー!」
唯のキューを受けて、曲が始まる。曲が始まったのを確認して、唯はカフボックスのレバーをオフにした。それに全員が追従する。
「茜ちゃん、良かったよー、座って?」
「はいっ! 緊張しました!」
茜は椅子に座ると、ほうっと息をつく。
「だいじょぶ! お客さんもだいぶウケてるよー? ほら!」唯はブースの外を示す。「茜ちゃん、手ふったげて?」
言われた通りに、茜は笑顔でブースの外に向かって手を振った。観覧者の何人かが茜に手を振り返す。
「順調ですね。日野さん、緊張してるって言ってましたけど、初めてでも落ち着いてるじゃないですか」
コントロールルームの中、ディレクターが言う。
「いやあ、唯と番組の力が大きいですよ。さっき立ち上がったのだって、きっちりフォローしてもらいました……っと」
俺は身を乗り出す。
裕美の表情がこわばっていた。背筋も少しだけ丸まってしまっている。
ラジオはまだ曲を流している最中だ。俺は裕美の緊張の原因を探り――すぐにそれにたどり着いた。
ブースの外、レコード店内から観覧しているギャラリーのうち、制服姿の女子三人組が、ブースの中を見ながら談笑している。三人のうちの一人が、額を指さして仲間と盛り上がっていた。
裕美は卓上の資料に視線を落として、ときどき、店内とを隔てる窓のほうを気にしていた。
裕美のとなりに座っている荒木比奈が、俺のほうを見る――
――そして、時間は現在に戻る。不安を残したまま、曲は終わり、裕美を除く全員がカフボックスのレバーをオンにする。比奈がすぐに裕美の肩を叩き、裕美は慌てて自分もカフボックスを操作した。
「んー! ほんとにすっごくいい詩だったね! こーんなかんじで、みんなのレコメン曲流してアゲアゲで行くから、よろしくちゃーん! それじゃ、今日はゲストいっぱいだから、どんどんいくよー、つぎ、ほたるちゃんよろー!」
「あ、はい。私の好きな曲は……」
ほたるが自分のエピソードと、想い出の曲を紹介していく。
「……関さん、大丈夫ですかね?」
俺のとなりのディレクターが心配そうに尋ねた。
俺はブースの中の関裕美の表情をうかがう。
「曲のあいだにキャストに連絡もできますけど」
PAがブースから視線を外さずに行った。
「そうですね……」
俺は考える。
裕美を引っ込めるのも、俺が外まで出て行って裕美の緊張の元たる客をブースから離すのも簡単なことだ。
だが、それでは裕美は前に進めない。
疑心暗鬼を生ず。ブースの中からは、ギャラリーの表情は見えても、声は聞こえない。あの制服女子三人組がどんな話をしているかもわからない。裕美に対して好意的なのか、逆に悪意があって額のことをバカにしているのかも、答え合わせは不可能だ。
答えはない。悩んで解決できる問題ではない。だから裕美自身が、前に進むしかない。
俺は茜たち四人と、唯の表情を見る。
全員、笑顔ではあるが、表情は真剣だ。
俺も覚悟を決める。
「そちらが大丈夫であれば、まだ続行させてください。ほんとうにまずいときには、ストップをかけます」
「了解です」
「たぶん――あいつらはもう、弱くはないですから」
言いながら、俺は二度目の視線を送ってきた比奈に対して、目で合図を送った。
比奈が俺の意図を汲んだかどうかはわからないが、ひとつ頷く。――それと同時に、比奈の向こうに見えている唯が、俺を見て、にっと笑った。
「んんー、とーっても、しっとりしたムーディーな曲だったねー。 このスタジオ、ゴーカなホテルのレストランになったかと思っちゃった! ほたるちゃん、オトナじゃーん!」
ほたるのリクエスト曲が終わり、唯はほたるに向かって目を細める。
「すいません……ラジオの雰囲気、大丈夫でしたか……?」
ほたるは恥ずかしそうに笑いながら、唯に尋ねた。唯は大きく頷く。
「ぜんぜんオッケーだよー! アゲアゲな曲もいいけどー、ゆいはスローな曲も大好きだし、リクエストしてくれるゲストさんやリスナーさんもいっぱいいるし! 憧れちゃうよねー、低い声のダンディなおじさまにエスコートされちゃってさー、あまーくささやかれちゃいたいよねー、ぎゅって手なんか握られちゃったりして?」
言いながら、唯は手を繋ぐ身振りをする。それから、ぱちんとウインクした。
それで、ほたるはなにかに気づいたように小さく口を開いた。ほたるは椅子の下でそっと手を伸ばし、隣に座る裕美の手に、自分の手のひらを乗せた。
机の上の資料をじっと見ていた裕美が、はっとしたようにほたるを見た。
ほたるは穏やかに、裕美に向かって微笑む。
「じゃ、スタジオのアイドルのみんながすっかりしっとりいーオンナになったとこでー、つぎは春菜ちゃん! アゲ曲の紹介の前にー、ね、春菜ちゃんは、自信失っちゃったり、アガらないときって、ある?」
「ええと……もちろん、ありました」
春菜は資料を手元に置く。もともと大枠しか決められてないとはいえ、このことは台本にはない。唯の判断だろう。春菜なら対応できると睨んだか。
春菜は裕美のほうを見てから、話し始める。
「私、眼鏡が大好きで、だけど、それが伝わらなかったり、眼鏡の私が否定されるかもしれないことが怖くて……」
「ね、ね『ありました』ってことは、いまはだいじょーぶなん?」
「ううん、いまでも、ときどき迷うことはあります。でも、前より強くなれました。教えてもらったんです。自信がないままじゃダメだって。眼鏡は私に前を向かせてくれる、でも前を向くのは私自身です。私が眼鏡を大好きなことを、私が信じてあげなきゃいけないんだって」
「そっかぁー」唯は感慨深げに頷く。「でもわかるよー。ゆいもこんな感じだと、ふまじめとか、ナメてるとか、かるーく見られちゃうこともあってさー。でも、ゆいがいっちゃんイケてるのはゆいが一番楽しくやってるときだから! やっぱ、ゆいも春菜ちゃんも、自分らしくやってるのがいちばん最高で、みんなを楽しませられるってことだよね!」
唯は無邪気に笑う。茜たちも大きく頷いた。裕美は顔をあげ、真剣に春菜と唯のほうを見ている。
「そんな春菜ちゃんのアゲ曲は、どんなときにきいてるー?」
春菜は眼鏡の位置を正し、ひとつ呼吸をしてから話し始める。
「私は、自分が元気を出したいときに聞いてます! 私のあこがれのアイドルの曲なんです。アイドルをしていると……ううん、アイドルだけじゃなくて、みんな毎日を生きていると色んな不安があると思うんです。この曲は、女の子がなかなか自分に自信が持てないけれど、でも大好きな人への強くて純真な気持ちが溢れちゃうって詩で、前向きな気持ちをたくさんたくさん、同じ言葉をなんどもなんども繰り返して、いっしょうけんめいに前に前にって歌ってるんです。とっても力をくれる歌なんですよ!」
「よし、じゃー春菜ちゃんのリクエスト、いってみよー、ミュージックスタートー!」
「くっくっ、これだから、ラジオってほんと、最高っすよね」
ブースの中、PAが嬉しそうに卓を操作する。
「まったく」ディレクターが頷いた。「ゲストも良ければ、なおさらね」
「いやあ、実力のあるパーソナリティと信頼のスタッフあってこそ、ですよ」俺も負けじと褒める。「けど、もう一歩……裕美には、自分の答えを見つけてもらわなきゃいけない」
俺はブースの中の裕美を見つめた。
「行け、裕美」
俺はつぶやく。声はレコーディングブースには聞こえていないはずだった。それなのに、裕美ははっとしたようにこちらを見た。
裕美が俺を見て、なにかを感じ取ったように、俺には思えた。
曲がはじまり、六人はマイクを切る。
「みんな、ありがとう」最初に口を開いたのは裕美だった。「私、ほんとにみんなに助けられてるね。唯さんも。……もっと笑顔、がんばらなきゃ」
「ゆいは楽しくおしゃべりしてるだけだよー、裕美ちゃんも、せっかくだし楽しんでっちゃって!」
唯は裕美に向かって投げキッスする。それで、裕美の表情が和らいだ。
「裕美ちゃん」
比奈は自分の手元の資料を裕美に示す。そこにはいつのまにか、裕美の似顔絵が描かれていた。しかめっ面の裕美と、笑顔の裕美。デフォルメされた自分の姿を、裕美は見つめる。
「私、こんな顔してた? ……やっぱり、笑顔のほうがいいよね」
弱々しく笑う裕美に、比奈は穏やかな表情で首を横に振る。
「笑顔になろうと無理をすることはないと思うっスよ。どっちも裕美ちゃんで、どっちも魅力的っス。それに、漫画やアニメでも、ずっと笑顔だけのキャラって、かえってブキミなもんっスよ」
言いながら、比奈は持っていたペンで裕美の手をなぞる。ペンにはキャップが着いたままなので、なにを書いたのかまでは、俺からは遠くてわからない。
「そうですっ!」茜が身を乗り出すようにして続く。「アイドルだっていっつも笑顔だけじゃあじゃないはずです、悲しいときも嬉しいときもあって、自然な裕美ちゃんがいちばんですよ!」
「お芝居のレッスンしているときの裕美ちゃん、いっつも表情豊かで、すごいなって思ってます」
ほたるは言いながら、小首をかしげて微笑んだ。
「いろんな、表情……そっか、私、無理して笑顔でいようって思ってたんだ……哀しいときも嬉しいときも、自然に。楽しいときに笑うのも、私のままでいいんだよね」
裕美はほたるの目を見つめて言い、頷いた。
ほたるは裕美がもう大丈夫だと思ったのだろう、裕美の手に添えていた自分の手をそっと離す。
裕美は姿勢を正して、目の前を穏やかな顔で見つめて、ふっと微笑んだ。
「曲あけます、準備してください」
PAの合図がかかる。六人はお互いに頷き合うと、カフボックスのレバーに手をかけた。
唯が裕美を見つめる。
「もしまだだったら、ゆいがつなぐよ?」
裕美は唯を見つめ返す。
「ううん、大丈夫」
裕美は言う。自然な笑顔だった。曲がフェードアウトしていく。六人はマイクを入れた。
「ああーっ、ここでおしまいでしたか……」唯より早く、春菜が残念そうに言う。「この曲、一番最後まで聴くと、歌詞に眼鏡って出てくるんですよ! みなさん、ぜひ聞いてくださいね!」
「あはは、ってことで、眼鏡ちょーラブな春菜ちゃんのアゲ曲でっしたー! 続きましては、裕美ちゃん! なんだけどー、そのまえに、ゆいぜったい裕美ちゃんに聞こって思ってたことがあったんだー! 裕美ちゃんのそのアクセ、めっちゃカワイイよね! プリティーなおでこのとこ、ヘアクリップと、首もとのネックレス! ずっと気になってたんだー!」
おでこ、と言われ、裕美はぴくりと肩を跳ねさせた。裕美は窓からギャラリーをちらりと見る。俺も見た。さっきの女子学生たちはまだ、そこにいる。
裕美はもう一度唯をへ向き直る。
それから、自然な笑顔を見せた。
「ありがとう。これはね、私がつくったの。私、アクセサリー作りが趣味なんだ」
「えっマジ!? すっごーい! だってほら、公開収録見てるみんなは見えるよね、すっごいかわいいの! ね、もっと見せてあげてよ! ラジオで聴いてるひとはねー、ね、あとでサイトに写真、のっけていい?」
「うん、大丈夫」
裕美は言いながら、外のギャラリーにアクセサリーが見えやすいように姿勢を整え、ギャラリーに向かって手を振った。
照明を受けて、裕美がつけている、傘のような白と赤の花を水晶にとじこめたようなアクセサリーがきらめいた。
「どーやって作ってるの? ゆいにもできる?」
「これはね、この中心の部分はレジンで……」
それから少しのあいだ、裕美は唯と手作りアクセサリーのトークを続けた。レコーディングブースの窓の向こうの店内では、主に若い女性のギャラリーが興味深そうに二人のトークに聞き入っている。その中には、さきほどの女子学生たちも混じっていた。
「もう、大丈夫そうですね」
ディレクターが俺に笑いかける。
「ええ」俺はブースの中を見る。茜と比奈と春菜が、こちらを見て親指を立てていた。「答えに、たどり着いたみたいです」
「それじゃ、裕美ちゃんの曲、いってみよー!」
トークのあと、唯は裕美にリクエスト曲のタイトルをコールさせた。
曲が始まり、六人はカフボックスをオフにする。
「ちょーアガったね! ほらあっち、ディレクターちゃんも、みんなのプロデューサーちゃんも、めっちゃいー顔してるよ?」
唯はコントロールルームのほうを示す。
裕美とほたるがこちらを向いて、ふたりとも幸せそうに微笑んでいた。俺は手を振って応える。
そのあと、ラジオは最後に比奈のリクエスト曲を流した。比奈がリクエストしたのは魔法少女モノのアニメの主題歌だった。事前に聞いていたリクエストの理由は作画やストーリーが素晴らしいから、と俺は記憶していたが、比奈は「魔法少女モノは女の子が仲間との絆の力で強くなって、変身するのが醍醐味っス」と説明していた。
エンディングに茜たち五人のユニット活動を再度告知して、番組は終わった。
公開収録の恒例ということで、窓の向こうのギャラリーたちも含めて出演者で写真を撮った。約束通り、裕美のアクセサリーのアップも撮影する。それらの写真は番組ウェブサイトにアップロードされるとのことだった。
「おつかれちゃーん! めちゃ楽しかったよー!」
唯は本番中と変わらぬテンションで、控室の五人をねぎらった。
「そいえばねー、今日のラジオはゲストたくさんでおたよりの時間取れなかったんだけど、番組におたよりいっぱい届いてたって! あとでうちのディレクターちゃんから送っとくね?」
「あっ、俺。はいはい、おくっときますよ」ディレクターがやれやれといった顔をする。「プロデューサーさんのアドレスでいいですか?」
「お手数かけますが、お願いします」
俺は頭を下げる。
「んで、みんな宛のもあったから、すぐ教えたくなっちゃって!」唯は折りたたまれた紙を拡げる。プリントアウトされたメッセージの文面だろう。
「いっこ紹介するね?『唯さん、ゲストのみなさん、こんにちは。先日、ゲストのみなさんをライブで初めて見ました。あの日以来、みなさんのうちの誰かが出る番組が気になってしまい、できるだけみるようにしています。今日の放送も、楽しく聞かせてもらってます。みなさん、がんばってください!』だってさ! ほら、ほかにもたーくさんだよ!」
言って、唯はプリントアウトされたメッセージを茜に渡す。
茜に渡された紙を、ほかの四人は両側から覗き込むように見る。
「私たちのこと、見てくれているひと、居たんですね。……うれしい」
ほたるがそっと目を伏せた。比奈がその髪を優しく撫ぜる。
「ちょっと、アイドルやってるって、実感してきたっス。おもったより、嬉しいもんっスね」
真剣な表情でメッセージを読み耽る五人だったが、ふと裕美が四人から離れて、俺のところに歩いてくる。
「プロデューサーさん」裕美はぺこりと頭を下げる。「ありがとう。さっき、ラジオが流れてるとき、背中、押してくれたよね。声は聞こえなかったけど……そんな気がしたの」
「そうか? 応援は確かにしてた。けど俺は何もしなかったぞ。裕美が自分の力でたどり着いたんだよ」
「ううん」裕美は首を横に振る。「私一人じゃない。みんなが居てくれたから……茜ちゃん、比奈さん、春菜ちゃん、ほたるちゃん……それに唯さんと、プロデューサーさん、スタッフさん。たくさん助けてもらってるよ」
裕美はいまだメッセージを読み耽る四人のほうを見る。
「私、ギャラリーの人に笑われてるんじゃないかって、怖かった。でも、あとで写真とったとき、みんな素敵な笑顔をしてた。私が勘違いしてただけ。私が私に自信を持てないだけだったんだ。いまは、ぜんぜん違って見える。前を向くだけで、こんなに世界って、きらきらして見えるようになるんだね」
「そうだな」
「応援してくれてる人達もいるってわかった。たくさんの人に笑顔をもらったから、今度は私が、誰かに笑顔をあげられるようになりたい。きっと、それでいいんだよね」
「ああ……十分だ。そういえば」俺は一つ残った疑問を尋ねてみることにする。「さっき、ブースの中で、比奈は裕美の手になんて書いてたんだ?」
「さっき?」裕美は一瞬考え、ああ、と思い出したように言って、俺に掌を見せる。「『No.1アイドル』だって。偉そうにするほとじゃないけど、自分がナンバーワンって自信を持つくらいでちょうどいいって、励ましてもらったの。……私、このユニットに参加できてよかった。これからも、頑張るからね」
裕美はそう言って、四人のところに戻っていった。
その後ろ姿に、迷いや恐れはもう、見えない。
・・・END
そうして、俺のデスクに置いているフォトフレームには、新しい写真が増えた。
唯を含めた六人全員が、楽しそうに笑う写真。その後ろで、ギャラリーも全員楽しそうにしている。
この日以降の裕美の写真は、更なる魅力で溢れていくことになる。