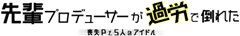
人は慣れていく。
なりたかったはずのものになれなかったことに。
なりたかったはずものになれなかったアイツが、もうそばにはいないことに。
慣れなくては前に進めない。けれど、慣れたとき、確実に何かが終わる。
終わったらもう戻れない。
「……いまだに、飲み込めてないっス」
俺が運転する車の助手席で、荒木比奈はフロントガラスを硬い表情で眺めながらつぶやいた。
「もう一回説明するか? ティーン向けのファッション雑誌で、モデルの仕事だ。指定の衣装で撮影。先方もこちらがファッションモデルではないことは判ってるから、気張らなくても」
「そうじゃないっス、日陰者のアタシが、モデルってのがまだ……ってプロデューサー、わかってアタシのことからかってるっスね!?」
比奈はこちらを睨みつけた。
「まぁまぁ、大丈夫ですよ! 私も前にちょっとだけ写真のお仕事しましたけど、とっても楽しかったですよ! 自分で思っているよりもずっと綺麗に撮ってもらえますし!」
後部座席右側に座る上条春菜が比奈をなだめる。
「今日はすっごく楽しみにしてたんです! なにせ、今日のお仕事はみんな!」春菜はそこですこしためを作る。「っ眼鏡ですから!」
「……なるほど」研ぎ澄まされた声が車内の緊張感を高める。「今日のメンバーは、そういう趣向で選ばれたの?」
言いながら狭い車内で足を組み替えたのは、美城プロダクションのアイドルの一人、八神マキノだった。後部座席の左側、春菜のとなりに座っている。マキノは右手の人差し指をこめかみのあたりに当てて、真剣な眼でバックミラーごしにこちらを見ていた。
「……いや、たまたまだ」
「そう」
マキノは短く返事すると、そのまま窓の外へ視線を向けた。
「アタシの宣材写真、そもそも眼鏡かけてないですし……ところでアタシたち、ユニット外の活動もあるんスね」
比奈の疑問に、俺はうなずく。
「ああ。むしろユニットは楽曲やイベントのコンセプトに合わせた一時的な組み合わせだと考えたほうがいいかもしれないな。いまの五人のユニットは、先輩……前のプロデューサーが企画した新曲に合わせて組まれたユニットだ。これから美城で活動していくとなると、ほかのアイドルとの絡みも増えていくはずだぞ」
「なるほど……とりあえず、今日はマキノさん、よろしくっス」
「ええ、よろしく」
マキノは比奈に微笑みかける。さっきまで近寄りがたい雰囲気を放っていたが、こうして笑っているところをみると、大人びてはいるものの閉じているという印象はない。単純に緊張していただけなのかもしれないと俺は考えた。
「同じ眼鏡アイドルとして、今日ははりきっていきましょう!」
まとめた春菜の一声で、これまでやや張り詰めていた車内の空気が緩んだ。
ちなみに俺の視力は悪くないのだが、朝の集合時点で春菜から伊達眼鏡をかけることを強要されている。
「今日のカメラマンは業界ではそれなりに名が通っているから、プロダクションとしてもしっかり成果を出しておきたい仕事だ。とはいえ、さっき比奈に言った通り、今日のメンバーは、モデルが仕事の中心ではないことは先方に伝えている。リラックスして臨んでくれれば、それで十分だろう。スタイリストをはじめとした各スタッフもプロだ、言うとおりにしていれば大丈夫さ」
「そうは言っても、やっぱり緊張はするっス……」
比奈はそういって深く溜息をついた。
都心から車で数十分。都内ではあるが、郊外のような落ち着いた雰囲気の街並みの中に存在する撮影スタジオに入る。すでにスタッフの大部分がスタンバイしていた。三人に楽屋で準備をさせているあいだ、俺はスタジオの全体を観察しておく。
よく芸能ニュースでみるような、スクリーンをバックにライティングが整えられた広めの写真スタジオが中心だが、室内はログハウスのように温かみのある木目調のデザインで、ハウススタジオとしても機能する。
ディレクターズチェアとテーブルが置かれたあたりに、買っておいたドリンク類と資料を配置した。動線や小道具の位置もざっと確認する。特に気になる点はない。これまで同行した撮影現場と同程度の規模だ。
「モデルさん準備OKでーす!」
楽屋の扉が開き、スタイリストの声がスタジオ内に響いた。メイクの済んだ三人がこちらに歩いてくる。
「よろしくおねがいしまーす!」
朗らかに挨拶したのは春菜だった。シャツとスカートでカジュアルにまとめている。ファッションとしては素朴だが、春菜の気取らない雰囲気によくマッチしている。ほかの二人がこの格好だったならむしろ不自然に映るだろう。
「よ、よろしくおねがいするっス……」
その後ろから背を丸めて出てきたのは比奈だ。まだ人から見られるということに慣れていないらしい。俺がジェスチャーで姿勢を正すよう伝えると、気まずそうに少し目を細めてから、背筋を伸ばした。比奈は暖色系のニットとフレアスカートで、春菜よりもやわらかい雰囲気に仕上げられている。オレンジのセルフレームの眼鏡をかけているが、あれはスタイリストではなく春菜が用意したのだろうか。
「ふふ、計算の通りね」
最後に出てきたのはマキノだった。学校の制服のようなイメージのブレザーとスカートだった。いったいなにを計算していたのかはわからないが、スタイル、姿勢ともに整っているマキノに着せれば、学生服は着る人物の美しさを浮き立たせるものであるということが自然と理解できる。
「三者三様だな」
「でも全員眼鏡です!」
俺の感想にかぶせるように、春菜が得意げに眼鏡のテンプルをつまんだ。
「スタジオのリア充っぽい雰囲気……やっぱりまだ慣れないっスね」
比奈はあたりを見渡している。
「俺だって慣れないさ、非日常だからな。緊張するのが普通だろう。春菜やマキノだってそうじゃないか?」
俺が話を振ると、二人はそれぞれに少し考える。
「そう、かもしれないわね」マキノはスクリーンのほうを見ながら言った。「面白い分析だと思うわ。どんなに事前にリサーチしても、完全に普段と同じようには過ごせない。ライブと同じね」
「私も……実はまだ、慣れないです」
春菜が恥ずかしそうに笑う。
「そういうもんっスかね……」
比奈が苦笑いした。これで多少緊張がほぐれたならよいのだが。
「カメラマンさん到着しましたー! おはようございます!」
入口付近から声がかかり、追従するスタッフたちのおはようございますの声の中、俺たちはいっせいにそちらを注目する。長身で白髪の混じったヒゲを蓄えた、ハットをかぶった細身の中年男性が、スタッフたちに手で挨拶をしながらスタジオへと入ってきた。今日のカメラマンだ。
「おはようございます、美城プロダクションです。今日はよろしくお願いします」
俺はカメラマンへ礼をして、名刺を差し出す。カメラマンはああ、と返事をしながら、つまらなさそうに俺の名刺を受け取った。
「そっちが今日のモデルさんたちね」
「よろしくおねがいします!」
三人の声が重なってスタジオに響いた。
「ん、さっそく、やってこっか」
カメラマンは軽く言いながら、機材のトランクを開けて準備を始める。
「お願いします」
「順番とかある? これ資料かな」カメラマンはテーブルの上の資料をとると、ぺらぺらとめくった。「聞いてたことと変わんないよね? じゃ……」
言って、カメラマンは三人を順番に見た。
「……キミからにしよ」
カメラマンはマキノに声をかける。マキノは「はい」と短く返事をした。心なしか声に緊張が混じっている。
「事前の調査のとおり……」
マキノはほんの少しうつむいて、周りに聴こえるかどうかの声で、小さくつぶやいた。それから顔をあげる。
「……マキノ」
俺に声をかけられて、マキノは立ちどまる。
「なに?」
「あー……」話しかけておいて、俺は困った。緊張をほぐそうとしたものの、マキノのことを知らなさすぎてかける言葉が思いつかない。「その……気楽にな」
苦し紛れに言った俺を観ながら、マキノは目を丸くして、それから軽く噴き出した。
「……次からは、あなたのことももっと調査するわ。……ありがとう」
マキノはそう言って、カメラマンの前へと歩いて行った。
「んじゃ、行くね」言いながら、カメラマンはシャッターを押していく。「うん、いいね、すこし顎を引いて……手は自然に、そう、いいよ」
簡潔に指示を飛ばしながら、カメラマンはマキノの写真を撮り続けた。比奈と春菜は次の自分の番に備えてだろう、真剣にそのようすを眺めている。
ポーズを変え、シーンを変え、マキノの撮影は続いた。マキノもだいぶ慣れたようで、同じ涼やかな表情でも、その内側からは緊張が消えていく。少しずつ、カメラマンとのやりとりもかみ合ってきた。時にはマキノの提案を取り入れ、マキノとカメラマンのあいだで試行錯誤しながら撮影が進む。カメラマンのテンションも次第に上がってきた。
「ん、んー……」カメラマンは悩むような唸り声をあげた。「たとえば、ちょっと眼鏡、取ってみようか?」
「えっ」
明らかに不安の混じった小さな声を漏らしたのは、マキノではなくて俺のとなりに居た春菜だった。
マキノはちらりと春菜のほうに視線を送って、それからもう一度カメラマンのほうを見た。
「私は、違うと思うけれど」
マキノはそう言ってから、眼鏡をはずしてみせる。
数秒の沈黙。
「うん、確かに。キミの言う通り、ちょっと違ったみたいだ。眼鏡かけて」
カメラマンの指示の通りにマキノは眼鏡をかけ、撮影が再開する。
俺は横の春菜を見た。少し表情が暗い。
「あの、プロデューサー」
春菜がこちらを不安そうに見ていた。
「……どうした?」
「今日は、その……」
春菜はそこまでで口をつぐみ、その先を言わなかった。
俺も、春菜の言葉の先を探ろうとはしなかった。春菜の心配は判っている。というよりも、春菜の心配は恐らく俺がいま心配していることと同じことだ。春菜は自分が眼鏡をはずすことを求められないか不安に思っている。
俺は内心で頭を抱えていた。最初に春菜たちに説明したとおり、このカメラマンはそれなりの大御所だ。変に機嫌を損ねて、プロダクションの評判を下げたくはない。一方で、春菜の眼鏡にかける情熱は春菜のアイデンティティだ。
「まぁ、大丈夫さ」
俺は間の抜けた声で春菜に言う。なんの根拠もない。春菜はそれ以上話しかけてはこなかった。
マキノに続いて撮影が始まったのは比奈だった。比奈は「心が無理って思ったらその時点で負け……行ってくるっス」とつぶやいて、やや硬い動きでカメラマンのもとへと歩いて行く。
「むっ……すこし……なんだろうな、うーん」
カメラを構えたカメラマンはマキノの撮影の時よりも明らかに表情を険しくして比奈を見た。
「よ、よろしくおねがいす……します」
比奈の声には緊張が見て取れる。無理もない。ほんの二カ月程度前まで素人だった人間だ。
「ふーん、ともかくはじめよう、そこ座ってみて」
「はい」
比奈はカメラマンの指示の通りにする。
「ああ……違う、そうじゃなくて、足はそっちに」
カメラマンの声にいら立ちが混ざる。比奈は言われた通りにするが、それもイメージと会わないのか、シャッターを切る合間でカメラマンの厳しい指示は続いた。
撮影から数分経ったが、比奈の表情は硬いままだ。
「比奈さん……」
春菜も不安そうな声を漏らす。そのときだった。
「おっ! 今の、いいね! それでいこう!」
カメラマンは急にトーンを明るくして、比奈のポーズを褒めた。
「えっ、えっ?」比奈は困惑の声をあげる。「そ、そうっスか?」
「ああ、いいよ、そう、そのまま……いいね」
カメラマンは嬉しそうにシャッターを切っていく。
「へ、へへ……」
比奈の表情が緩み、笑みがこぼれた。
「あっ、可愛い、比奈さん……」
春菜がぽつりと漏らす。
俺も同感だった。緊張から放たれて弛緩した表情と姿勢とが、比奈の魅力を高めている。
「リサーチによれば、あれが彼の技術らしいわ」
いつのまにか隣に立っていたマキノが得意顔で言った。
「なるほどな」
納得できた。さすがは名の通ったプロということだ。被写体に応じて、その魅力を引き出すためのアプローチや話術を変えているんだ。比奈は撮影開始前、明らかに緊張し固まっていた。だからまず厳しい声色でより緊張感を高めたあと、一気に弛緩させて魅力を引き出した。
「床にお座りする感じで、足は楽にして」
「こうっスか?」
「そうっ! いいよ、もっと力抜いていい、笑顔見せて」
「急に笑顔とか言われても、は、恥ずかしいっス……」
比奈がそう言ってはにかんだ瞬間を逃さず、連続でシャッターが切られる。
「よーし」カメラマンは満足そうに微笑む。それから比奈の顔をじっと見た。「うん、キミもちょっと一回眼鏡、はずしてみよっか」
瞬間、場にわずかな緊張感が走った。比奈は俺と春菜のほうをほんの少し見てから、ゆっくりと眼鏡をはずす。
「うん、それもいいなぁ!」
カメラマンは再びシャッターを切り始めた。
確かに、比奈は普段眼鏡をかけているが、眼鏡をはずしてもそのキャラクターに致命的な影響は与えない。
だが今の問題は、別のところにある。俺は春菜のほうを見た。春菜は眼鏡をはずした比奈をじっと見ている。両手はぎゅっと握りしめられていた。
このままではまずそうだ。そう判断した俺は、比奈の撮影が終わるころテーブルの上において置いたドリンクをひとつ手に取った。
「お疲れさま! すごくよかったんじゃない?」
「恐縮っス……ありがとうございました」
撮影が終わり、比奈はほっとした顔でカメラマンに礼をした。
「さて、それじゃ……」
「いやーっ、お疲れ様です、ありがとうございます!」
俺はカメラマンの言葉にかぶせるようにして、声を大にして近づいていく。言いながら、ドリンクのキャップを開けて、カメラマンに差し出した。
「とっても素晴らしい撮影でした! うちのアイドルたちめちゃくちゃ綺麗にとってもらって、ありがとうございます!」
カメラマンは目を丸くして、差し出されたドリンクを受け取った。
「そう? 大げさだよ」
「いやいやいや、そんなことないです! 自分でも社内カメラマンとかに宣材写真とか手配しますけれど、それとも段違いで恥ずかしいくらいですよ、ハハハ……ところでなんですけども!」
俺はできるだけ、相手が会話に入る間をつくらないように言葉をつづける。
「ちょっとここらで、小休止入れませんか、時間も経ちましたし、お疲れでは? まだ撤収まで時間に余裕ありますし、そちらは午後も撮影があると聞きました。全体はマキで進んでますんで、どうでしょう?」
どうでしょう、に「お願いします」のニュアンスをほんのすこしだけ混ぜて、俺はカメラマンにお伺いを立てた。
「ん……そうだなぁ……」カメラマンは斜め下のほうを見て少し考えてから言う。「じゃ、お言葉に甘えて、ちょっと休憩しようか」
「ありがとうございます! じゃあ……」俺は時計を見る。「二十分後までには、こちらスタンバイ完了しておきますんで!」
「はい。じゃ、ちょっと外でタバコしてこよっかな」
「あーっ、すいません気が利かず、普段吸わないもんでタバコも火も持ってなくて……」
「いい、いい、大丈夫だよ、ありがとね」
言って、カメラマンはスタジオの外へ歩いて行った。その姿を見送り、ドアが閉まるのを確認する。
「ふーっ」
俺は大きく息をついた。
「プロデューサー、ありがとうございます」
春菜がこちらを見ていた。俺が時間を稼いだことがわかったらしい。
「とりあえず、楽屋に入ろう」
俺が楽屋の扉を示すと、春菜はうなずいて楽屋へと向かった。
春菜、比奈、マキノとともに楽屋に入ると、俺はがっくりと肩を落とした。普段やらないようなキャラクターを演じるととても気疲れする。
マキノは俺たちから少し離れたあたりの壁に背あずけて、こちらを見ている。
「すいません、中断させてしまって」
春菜はやや暗い声で言う。
「いや、大丈夫だ。とりあえず落ち着いてくれ」
「春菜ちゃん……眼鏡のことを心配してるっスね? その……申し訳ないっス、アタシが断って流れを作っておけば……」
比奈の言葉に、春菜は首を振る。
「いえ、気にしないでください」
「ああ、比奈の撮影はあれでよかった。……マキノもな。気にすることじゃない」
「そうです。眼鏡のことは、私の問題です。撮影、二人ともすごくよかったです」
春菜ははっきりとそう言った。
「さて……春菜の撮影だが……眼鏡については、外す指示があるかもしれないな。前の二人にあった通り……な」
「はい、でも……」春菜は胸の前で握り拳を作る。「眼鏡は、外したくないんです。外した写真を撮って、それが採用されるかもしれないのは……」
春菜はうつむいて、そこから先の言葉を濁した。きっと、春菜自身が、その考えが特異なものであるということを理解している。
春菜の眼鏡に対するこだわり。それは春菜の最大の魅力であり、セールスポイントだ。
だが、モデルとしての仕事、アイドルとしての人格から離れ、ファッションを輝かせるための素材になり切る仕事には、そのこだわりは重要なポイントではなくなる。眼鏡をはずしてファッションが映えるなら、間違いなく眼鏡をはずすのが正解なのだ。
けれども、だからといってモデルは人格のない人形ではない。今回、この雑誌の仕事がモデルではなくアイドルを起用したのは、モデルよりも身近な存在の人格とともにファッションを紹介するためだろう。
「私をスカウトしてくれたプロデューサーさんも、眼鏡をかけた私を、魅力的だって言ってくれたんです」
春菜はぽつりと漏らした。
「眼鏡が好きで、でも眼鏡をかけた地味なアイドルなんていないから、眼鏡じゃだめかなって悩んでたところに、そのプロデューサーさんは背中を押してくれたんです。眼鏡のほうがいいって、眼鏡を好きなままでいいって」
「春菜ちゃん……」
比奈がそっと春菜の背に手を添える。マキノは真剣な表情でこちらを見ていた。
俺は少し目を細める。
これは春菜の今後に関わることだ。春菜がきちんと腹をくくらなくては、前に進めない。
「春菜」
俺は春菜の前に歩み出る。
「俺は……今、臨時でもお前たち五人のプロデューサーだ。春菜が眼鏡へのこだわりを持ってることで輝いているのはわかっている。俺もできるだけその意思を汲んでやりたい。けれど、春菜自身が感じているように、春菜の眼鏡好きが、今みたいに障害になることもある。そういうとき、一番ダメージを受けるのは春菜だ。眼鏡アイドルとして羽ばたければ一番いい。だけど、眼鏡へのこだわりが強すぎることで仕事が減る可能性だってあるんだ。ひょっとしたら……眼鏡へのこだわりが強すぎたことで、アイドルとして成功する道を逃すかもしれない」
春菜は俺の目を見た。不安そうな顔をしている。俺は続けた。
「もちろん、その逆もある。眼鏡へのこだわりを持ち続けて、その魅力で羽ばたける可能性だって。けどな、その道を選んだときは、ブレちゃだめだ。眼鏡へのこだわりを一瞬だって疑ったら、その瞬間に終わっちまう。厳しい道だぞ。……春菜が、決めるんだ。眼鏡アイドルで、行くのかを」
春菜は俺の目を見て、それから視線を下に落とす。
比奈はずっと春菜の背を撫でている。これ以上は、俺も、比奈も、もちろんマキノも、ほかの誰も、助けてやることができない。春菜が自分自身と向き合って、決めなくてはいけない。
そうじゃなきゃ――それ以上に覚悟を決めて戦ってるアイドルたちに、太刀打ちなんてできやしない。
「……春菜ちゃん」
春菜の背を優しく撫でていた比奈が、春菜の手を包むように握った。それから、真剣な眼で口を開く。
「まだ、アイドルなりたてのアタシがこんなことを言うのは、およびじゃないかもしれないっスけど」
比奈はひとつ呼吸を置く。
「自分にとって大事なことを決めなきゃいけないときって、色んな誘惑が襲ってくるもんっス。ああしたほうがみんなが喜ぶだろう、きっとうまくいくだろう、だからこっちを選んだほうがいいかもしれないって。でも、ほんとうに大事なのは自分自身の心っス。ほかは……全部、よけいなコトっすから。惑わされちゃ、だめっスよ」
「比奈、さん……?」
春菜は比奈の目を見る。見つめ返す比奈の眼は、じっと春菜を見据えている。
「一回でも誘惑に負けたら、つぎのチャンスなんて、二度と巡ってこないかもしれないっス。だから、春菜ちゃんは自分にとって大事な事だけを選んで、決めてほしいっす」
そこで、比奈はふっと表情を緩ませる。
「生意気言って申し訳ないっス。でも、春菜ちゃんよりちょっとだけ長く生きてるヤツの意見ってことで、受け取ってくれたらうれしいっス」
「……私にとって、大事なこと……」
春菜はもういちど、視線を下に落とす。それから春菜は呼吸を二、三度繰り返し、それから深く息を吐いて、止まった。
やがて、春菜はゆっくりと顔をあげた。
それから、目を閉じて、両手で丁寧に眼鏡の全体を包むようにする。愛おしそうに。数秒そうしたあと、春菜はまぶたを開いた。
レンズごしに俺を見つめる春菜の両目は、はっきりと意思を伴っている。
背筋がぞくりとした。
そういえば、先輩が言っていた。アイドルと接してると、急にそのアイドルが化けるときがあるのだと。
たぶん、いまのがそれだ。
「やります」春菜ははっきりと言った。「私、一番の眼鏡アイドルになります!」
「春菜ちゃん……」
比奈が安堵の声をあげた。少し離れたところでマキノが微笑んでいる。
「よし」俺は大きくうなずく。「わかった。俺も眼鏡アイドルの春菜をプロデュースする。眼鏡の写真だけを通すさ」
「プロデューサー……!」春菜はぱっと顔を輝かせた。「ありがとうございます!」
「さ、そろそろ戻るぞ。休憩は終わりだ」
俺はみんなにスタジオへ戻るよう促す。春菜は、笑顔で楽屋から出て行った。
「とても興味深いわね」マキノが言う。「まだ、解析できないの。いま、なにが起こったのか……でも、とてもいいものを見せてもらえたわ。ありがとう」
マキノは手を振り、楽屋から出て行った。
「ふぅ……」
大きく息をついた俺のとなりに、比奈がやってくる。
「思ったとおりっス」比奈は嬉しそうな顔をして言った。「プロデューサーは悪人にはなりきれない人っス、ちゃんとプロデューサーしてくれてるじゃないっスか」
俺は比奈のほうを見て、笑い返してやる。
「そりゃ、仕事だからな……でも比奈、比奈の言葉が春菜の背中を押したんだ。ありがとうな」
そう言って、俺は楽屋を出た。
扉を開けて、スタジオへと戻る。戻りながら、春菜をサポートするための覚悟を決めた。こんなとき、先輩ならどうするか。簡単だ、先輩なら単純に「春菜は眼鏡アイドルなので、眼鏡なしの写真はNG」と示すだけだ。
なぜなら、先輩は敏腕だから。それを言って通すだけのバックグラウンドがあるから。俺にはそれはない。名の通ったカメラマンに、ペーペーのプロデューサーと、売れっ子でもないアイドルが生意気を言っていい理由はなにひとつない。だから、それ以外の方法だ。
「カメラマンさん戻りました、再会でーす!」
スタッフの声がする。
「よろしくおねがいします!」
俺が言うより先に、春菜の明るい声が飛んだ。いつもの元気を取り戻したようだ。
「ん、じゃ最後のキミだねー」カメラマンは手早く一眼レフを準備し、スクリーン前にスタンバイしている春菜の前でカメラを構える。「まずは普通に、自然に立ってみて」
「はいっ」
シャッター音がひびき、春菜の撮影が始まった。
撮影は順調だった。小道具やポーズを変えながら撮影は進む。
それから、カメラマンは「ふーん」と唸って、カメラを降ろした。
「んー、キミもさぁ」
カメラマンは春菜の顔、眼鏡を見ている。
俺はスタジオに向かって身構えた。
「ちょっとその、眼鏡」
いまだ。
「いっやー、いいですね!」
俺は大げさにその言葉に割って入った。
「すっばらしーです!」そこまで言って、オーバーに自分の頭を叩いた。「て、あー! すいません、ついテンション上がっちゃって、撮影中に!」
「お、おお、いや」
カメラマンは目を丸くした。ふつう、撮影にこんなふうに割り込んでくる人間はいない。予想外のことが起これば、固まるのが一般的な反応だ。
ここまでの流れを観るに、このカメラマンが眼鏡をはずさせたりしているのは、単純に彼のテクニック上の手段のひとつであって、眼鏡をはずした姿へのこだわりというわけではないはずだ。
だから、その瞬間に割り込む。
それで眼鏡の着脱を不問にしてくれればいい。そうじゃなきゃ……そのときは頭を下げよう。
「うちの上条春菜の撮影、どんな感じっすか、ちょっとぜひ、経過見てみたくって」
「ん……」カメラマンは一眼レフの液晶モニターに写真を表示させる。「こんな感じ」
俺はモニターを覗き込む。四秒、写真が切り替わり続けるモニターを見つめる。
「素晴らしいです! 眼鏡と衣装とアイドル、こんなにカメラマンさんの技術で見えかたって光るもんなんすねー! 行きましょう、この組み合わせ最高です! このままこの眼鏡と衣装と勢いで最後まで撮影しきっちゃいましょうよ! ね!」
まくしたてたが、正直しっかり写真を観る余裕なんてない。緊張で心臓が口から飛び出しそうだ。
俺は春菜に向きなおる。
「春菜も、こんなに腕のいいカメラマンさんに撮ってもらえるなんて千載一遇のチャンスだぞ! その眼鏡と衣装で、しっかり撮ってもらえよな!」
「は……はいっ!」
「いやー、この眼鏡と衣装と、うちのアイドルの晴れ姿、俺もしっかり目に焼き付けときますよ! あ、すいません邪魔しちゃいまして、続けてください!」
「あ、ああ……じゃあ、続けようか」
「はいっ、おねがいします!」
そうして、撮影は再開された。これだけ強引に眼鏡と衣装がセットであるという流れを作ってしまえば、眼鏡をはずさせることは難しいだろう。俺の放った言葉は賞賛だけだ。カメラマンの意向に異を唱えたわけでもない。
俺の目論見が成功したのか、カメラマンはもう、眼鏡のことは言わなかった。そのまま、春菜の撮影は眼鏡をはずすことなく無事に終わった。
カメラマンから終了の宣言が出た瞬間、俺は心労から深く深く息をついて、思わず近くのディレクターズチェアに腰を下ろした。比奈がドリンクを差し出してくる。苦笑いしながら、俺はそれを受け取った。
無様なふるまいではあった。先輩みたいにはできない。だが、すべき仕事はした。俺にはこれが精いっぱいだ。
カメラマンがこちらに近づいてきたので、俺は慌ててチェアから立ち上がった。
カメラマンは穏やかに微笑む。
「おつかれさん。ボクはこのまま次の撮影がここであるから残るよ。そちらさんの撮影はざっとデータもチェックしたけど、大丈夫でしょ。編集さんにおくっとくね」
「はいっ!」俺は深く頭を下げる。「今日は、ありがとうございました!」
「ありがとうございました!」
春菜たち三人が、俺のあとに続いて礼をした。
スタジオを出ると、時刻はちょうど正午だった。とても天気がよく、雲一つない青空の中心に太陽が輝いている。俺は停めていた車のロックを解除する。三人に車に乗るよう促すと、春菜が俺の前にやってきた。
「プロデューサー、フォローしていただいて、ありがとうございました」春菜は嬉しそうに微笑む。「私、眼鏡は外したくないってちゃんと言おうと思ったんですけど、やっぱり一瞬戸惑っちゃって。プロデューサーが割って入ってくれて、嬉しかったです」
「ああ」
「私、もう迷いません」春菜は空を見た。「眼鏡をかけた私が、アイドルの上条春菜です。私自身がそのことを信じてあげなきゃ、だめなんですよね。スタッフやファンの人なら、私が眼鏡のことを大好きだって知ってる。でも、私を知らない人達の前では通じない。そういうときこそ、怖がらないで私が眼鏡大好きだってことを、アピールしなくちゃいけません」
「ああ、そうだな」
春菜は晴れやかな顔で微笑む。
「がんばります。眼鏡に恥じないために。いつか、眼鏡のフレームとレンズの向こうに、ファンのみなさんでいっぱいの、きらきらした、私の……私だけの景色を見ることができるように。そうだ、そのときはお客さんもみんな、眼鏡をかけてくれたら、いいと思いませんか?」
俺は笑って肯定の意志を示した。
「今日のこの青空といっしょに、今の気持ちをしっかり覚えて、忘れないようにします」
春菜の目指す瞬間が訪れるそのとき、俺がどこに立っているのかはわからないが、今はただ、春菜たちを支えてやろうと素直に思う。
「プロデューサー、まだ出発しないっスかー?」
比奈に尋ねられて、俺と春菜は一つずつうなずき合うと、車に乗り込んだ。
・・・END
――次のモデルの到着を待つスタジオの中、カメラマンは午前中の撮影資料をめくっていた。カメラマンの手は、上条春菜の資料のところで止まる。
「あー、こんなに眼鏡って書いてある。やっぱりあの子、眼鏡にこだわりあったんだねぇ。外すのNGだったのかなー」カメラマンは納得したようにうんうん頷く。「ってことは、あのプロデューサーの彼は、彼女の眼鏡をはずさせないために割り込んできたってことだね。もう、そのくらい、言ってくれたらよかったのになぁ」
「ははは、センセイを前にそれはなかなか言いづらいっすよー、大御所ですし」
アシスタントのスタッフが笑う。
「さみしーよね、こっちはそんなつもりはないからなんでも言ってくれていいのになぁ。この上条春菜って子、休憩終わってからいい顔してたんだよね。きっと、なにかきっかけがあったんだろうなー」
言いながら、カメラマンは自分のカメラの中の上条春菜のデータを表示させる。
モニタの中の春菜は、眼鏡をかけ、すがすがしい顔で微笑んでいた。