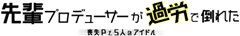
幼なじみのアイツは、いつもテレビの向こうのアイドルに憧れていた。田舎町だ、娯楽なんてなんにもない。だから、夜が更けてからはどの家もみんなテレビを見ている。テレビの向こうできらきら輝くアイドルになるのが夢なのだと、アイツはいつも話していた。
そして、ついにアイツはそれを実行に移すことにしたんだ。
あの頃はまだ、それがどんなに険しく、厳しく、辛い道かなんて、知らなかったから。
「行きましょうっ! プロデューサーさん!」
「早すぎだろ。待ち合わせの時間まで一時間以上あるぞ」
大声をあげながらプロデューサールームに入ってきた茜に、俺は応接用のチェアに座っているようジェスチャーで示した。
「いてもたってもいられませんでしたっ! 今日はついにっ! 私のはじめてのお仕事なんですよ!」
茜は頬を紅潮させ、鼻息荒くチェアに腰かけた。
「ああ知ってる。俺が取ってきた仕事だからな。体力仕事だ、温存しておいたほうがいいぞ」
そう言って俺はデスクのコーヒーカップに手を伸ばす。茜が待ち合わせ時間よりも早く来るのは毎度のことで、すでに驚くこともなくなっていた。さすがに、一時間以上早いのは新記録だったが。
アイドルユニット結成から一カ月とすこしが経った。茜たち五人は各種レッスンを順調に重ねている。合間をぬって、春菜、裕美、ほたるたちにはプロダクションから振られる各種の仕事をやってもらっていた。イベントスタッフや司会、ちょっとしたラジオ出演といったところだ。メンバーそれぞれが知られればユニット全体の後押しにもなる。
茜と比奈にも、単純な仕事から少しずつ振り分けていくことにした。茜は今日が初の仕事となる。比奈にも同じ仕事を打診してはいたが、即売会だからと断られてしまった。
「仕事の資料は読んだな?」
「はいっ!」
茜は元気よく返事をする。その目はエネルギッシュに輝いていた。
「復習しておくか。今日はショッピングモールで行われる子ども向けイベントのアシスタントだ。いわゆるヒーローショーってやつだな。ショーのメイン司会はプロダクションの別のアイドルが担当するから、指定の衣装を着ての販促物……風船配りが仕事だ。バイトみたいなものだと思っていい。それでも、プロダクションの名を背負ってやることだからしっかりな」
「はいっ!」
「屋内だから日差しにやられる心配もないし、難しくはない。それでも疲れたと思ったら無理せず休憩を入れろよ。……伝えるのはそのくらいだぞ。どうするんだ、あと一時間」
「そうですね……走り込みしてきますか!」
「体力を温存しろって言ってるだろ」
俺は茜にそう言って肩をすくめた。すこしずつ分かってきたが、この情熱が茜の魅力の源泉だ。俺は買っておいたペットボトルのお茶を手渡す。
「ライブの予習でもしていたらどうだ。ああ、でも声は張るなよ、イベントでは一日声を出し続けるんだ、思ったより疲れるぞ」
「わかりました!」
茜は自分の鞄からオーディオプレーヤーを取り出し、イヤホンをつける。俺も事務作業に戻るべく、デスクのモニターに視線を戻した。ほどなくして、茜の鼻歌が始まった。曲に合わせて、小さく体を動かして振付を確認している。
先週、茜たち五人にとっての初のステージが決まった。五人のための曲の完成よりも前のイベントなので、既存の曲を使う。プロダクションの看板のような曲で、所属したアイドルたち全員のための曲、どんなメンバーやユニットでも歌う曲だ。しばらくのあいだは、この曲と新曲のスケジュールを並行して進めることになるだろう。
プロデューサールームの中には、しばらくのあいだ、俺がキーボードを叩く音と、茜の鼻歌だけが流れ続けた。
とても、穏やかな時間だった。
都心から特急一本で行ける地方都市。休日のショッピングモールは人でごった返していた。吹き抜けの一階部分に設置されたステージの周囲では、慌ただしくイベントの準備が始まっている。
「美城プロダクションです、今日はよろしくお願いします」
「よろしくおねがいしますっ!」
茜の大声の挨拶は、あたりの人々全員の注目を集めた。
俺は愛想笑いしながらショッピングモール側の責任者に名刺を渡す。
「それで……メイン司会の弊社タレントが先に来ているはずですが、到着していますか?」
「ああ、スタッフ用のテントへご案内しました。狭くて申し訳ないです」
モール側の責任者はステージ裏手のテントを示した。
「とんでもないです」
「開始時刻になりましたらお呼びしますね」
言って、責任者は準備へと戻っていった。
俺は茜とともにスタッフ用のテントへ向かう。
「失礼します」
「今日はよろしくお願いします!」入るなり、元気のいい声が中から聴こえてきた。「美城プロダクションの堀裕子です!」
「ああ、我々も美城プロダクションだ、すこし遅れてしまってすまない」テントの中を見回す。堀裕子以外には俺たちしかいなさそうだ。堀裕子へ茜を紹介する。「こっちは今日のアシスタント」
「日野茜です! よろしくおねがいします!」
「開始までまだ時間があるようだし、二人ともゆっくりしていてくれ」
俺は茜に椅子に座っているように指示し、その場に立っていた堀裕子も椅子へと座らせる。
堀裕子。俺は記憶を掘り起こす。確か、超能力者だとかで売り出しているアイドルだったか。オーディションで超能力があると言って憚らなかったらしい。採用に至ったのは度胸が認められたのだろうか。まさか、超能力を信じて採用されたなんてことはないと思うが……ちらりと堀裕子のほうを見ると、その右手にはしっかりと銀色の先割れスプーンを握り締めていた。
「堀さん、それなんですか!?」
茜が堀裕子の持っているスプーンを見て興味深そうに尋ねた。
「私のことはユッコと呼んでください! そして、ふふふ……よくぞ聞いてくれました!」
堀裕子は再び椅子から立ち上がり、茜の目のまえにスプーンを突き出すようにする。
「私、なにを隠そう、超能力を持つサイキックアイドル、エスパーユッコなのです!」
堀裕子は自信満々に、一点の曇りもなくそう言った。
瞬間、場に沈黙が訪れる。
俺は堀裕子の言葉を扱いかねていた。事前にそういうアイドルだと知っていても、確かにあそこまで自身に満ちた表情で言われれば圧倒されるしかない。俺はしかたなく、テントの外を気にするふりをしながらそっと茜のほうを伺う――茜は目を丸くしていた。
「ちょ、超能力!? ほんとですか!」
「もちろんです!」
「ユッコさん、ということは、このスプーン……」
「さん、もいらないですよ! そのとおりです! さいきっくぱわーで……なんと、手に触れずに曲がります!」
「さいきっく! すごいですっ!」
自信満々の堀裕子と、聴いたことを全部真に受けている茜。マンガのような取り合わせだ。
「いいですか、茜ちゃん……これからこのスプーンに、私のさいきっくぱわーを送り込みます」
「はいっ……!」
茜は堀裕子の握る先割れスプーンを食い入るように見つめている。
「行きますよ……はっ! ムムムムム~ン……!」
堀裕子が念じるように、力のこもったうなり声をあげる。
「おおおっ……」
茜の口からも、興奮の混じった声が漏れていた。
曲がるわけはない……そう思いつつも、俺は横目でスプーンをちらちら見るのをやめられずに居た。
「ムムム……」堀裕子は苦しそうな声をあげる。「はぁ、はぁっ……まだパワーが足りないみたいですね……でも、高まりを感じます……もう少しで曲がる気がしますよ、さらにパワーを……ムムム~ン!」
「む、むむむ……!」
つられているのか、茜も堀裕子と同じように唸りだす。テントの奥からアイドル二人の苦しそうなうめき声だけが聞こえるのは、異様な状況だった。
俺は横目でスプーンを見ているが、やはりスプーンは曲がりそうもなかった。
「あの、すいません!」
「はっ、あ、はい!」
突然声をかけられて、俺の声は思わず裏返った。声のしたほうをみると、イベントのスタッフがテントの前まで来ていた。
「ひとまずスタンバイできましたので、打ち合わせとリハーサル、おねがいします!」
「あ、はい」
俺はテントの奥を見る。茜と堀裕子も、声がかかったことでスプーンにかまけるのをやめていたようだ。
「それじゃ、リハーサルだ、頼んだぞ」
「はいっ!」
茜と堀裕子の返事はひとつに重なった。
「あともう少しのところでしたね、きっと声がかかっていなかったら、スプーン曲げは成功していたはずですよ!」
片手に大量の風船の紐を握り締め、茜は興奮した様子でそう言った。
「その素直さは長所だとは思うけどな」
俺はそう言って、その先になにか続けようか迷い、結局なにも言わなかった。
俺と茜はイベント会場の入り口についていた。茜が会場に入ってくる人たちに風船を渡す。俺はイレギュラーへの対応と、風船の補充係だ。
俺たちのいるところからは、これから堀裕子が司会を務めるステージが見える。堀裕子はインカムをつけ、ステージ前の最後の打ち合わせに臨んでいた。
茜はステージ上の堀裕子を見ていた。
「お仕事が終わったら、今度こそ超能力を見せてもらいましょう、プロデューサーさん!」
茜はそう言って、自分でうんうんと頷いていた。
「どうかな、イベント後はどのアイドルもへとへとになるからな……体力が万全のときにしたほうがいいんじゃないのか」
「そうですか、そうですね……」
茜は残念そうにうなだれる。
「ほら、ここに立ってるときはもうアイドルだ。笑顔、笑顔」
「はいっ!」
茜は元気よく返事すると、姿勢を正して笑顔に戻った。
俺は腕時計を見る。イベント実施時刻の午後二時を回った。
「よし、イベント開始だ」
「どうぞー、ステージイベントやってまーす! 見て行ってくださーい!」
茜はよく響く大きな声であたりへの宣伝を始める。
人一倍大きく明るい茜の声が耳に届いたのか、あたりを行く人達がこちらを注目し始めた。
徐々に人が集まり始め、それから数分で、イベント会場は人でいっぱいになった。
俺は急いで風船をヘリウムガスで膨らまし、紐をつけて茜に渡していく。
茜は欲しがる子供たちに順番に風船を渡していき、ヒーローショーがあることを伝えていく。
「くださーい!」
「はーい、どうぞ! これからあっちのステージでヒーローショーをやりまーす! みていってくださーい!」
「次の風船」
俺が追加の風船の束を差し出すと、茜は「はいっ」と返事をしてそれを受け取る。このやりとりももう十回以上だ。
「すごい混雑だな……地域で一番のショッピングモールとはいえ、こんなに混むか? 都心のイベント並みだぞ?」
「風船もどんどん持って行ってもらえています! 楽しいですが、大変ですね!」
「ああ、でもそろそろイベント開始時間だ。始まれば子供はそっちに行くんじゃないか」
と、俺が茜に言ったときだった。
「みなさーん、こーんにーちわーっ!」
ステージに設置されたスピーカーから、堀裕子の声が響いた。
「こーんにーちわーっ!」
ステージに集まった子供たちの元気のいい返事が返る。その中でもひときわ大声を出し、俺の鼓膜を破壊しかけたのは茜……と思いきや、それよりもさらに大声の持ち主が、子どもたちの中に紛れていた。
「すごく元気な子がいますね!」
茜も目をぱちくりさせている。俺の位置からはよく見えないが、ぴょんぴょんと飛び跳ねて深い緑色の髪を揺らしている、小さな女の子の後頭部が見えた。どこかで見たような気もするが、顔が見えず、思い出せない。
「……気のせいか」
俺は誰へともなくつぶやいた。
「今日はあつまってくれてありがとう! 今日の司会をする、堀裕子です! ユッコおねえさんって呼んでください! いまから、この会場にすっごいゲストを呼びます! みんなでいっしょにお名前を呼びましょう! おねえさんのあとに続いてー!」
ステージ上の堀裕子がヒーローの名を呼ぶと、それに続いて割れんばかりの子供たちの声があがる。
ヒーローのスーツを身に纏ったアクターが舞台に現れ、場はさらにヒートアップした。
「すごい……」
イベントを訪れた客が全員ステージに注目し、ようやく忙しさから解放された茜がぼそりとつぶやいた。その目はしっかりと、ステージと自分との距離を見据えている。
その隣で、俺は茜に悟られないように、音を立てないように息を吸って、吐いた。過労で倒れた先輩はまだ戻ってこられない。茜たちをステージまで連れて行くのは、おそらく俺だ。
茜はステージまでの距離を見ている。俺には茜と同じだけの覚悟があるか――? 考えかけて、とどまる。状況に関わらず、仕事をするだけだ。今までやってきたことを。
「プロデューサーさん!」
「な、なんだ?」
突然、茜から話しかけられて、俺はそちらを見る。
「風船が足りなくなってしまいました!」
「あ、ああ」
俺は慌てて次の風船の束を茜に渡した。
事前に目を通したステージイベントのシナリオに特別なことはなかった。ヒーローがピンチに陥り、子どもたちの声援で復活、悪者を倒す。王道だが、王道は正解だから王道と呼ばれる。
イベントは終盤、殺陣の途中でヒーローがピンチに陥るシーンに差し掛かる。ヒーロー役のアクターは、悪者の攻撃をうけて、ステージの中央にがっくりと膝をついた。スピーカーからは不穏なBGMが流れ始める。ステージに入りこみすぎた子どもの怯えた泣き声が混ざった。
「ああっ、あぶない! よいこのみんな! ヒーローがピンチです! みんなの声で、ヒーローにパワーをおくりましょう! みんながいっしょうけんめいヒーローを応援してくれたら、このユッコおねえさんがさいきっくぱわーでみんなの応援をさらにパワーアップして、ヒーローに届けます! ユッコおねえさんが『せーの!』って言ったら、みんなで『がんばれー!』って、元気な声で応援してくださいね! いきますよーっ!?」
流れていたBGMが止まった。
堀裕子はステージからゆっくりと、イベント会場に集まっている子供たちの顔を見回していく。
その場にいる全部の目を、堀裕子自身に吸い付けようとでもするかのように。
それから、堀裕子は笑顔を作る。
「せー、のっ!」
すぅ、と息を吸う、無数の音が聞こえた。
その場にある空気が、子どもたちに吸い尽くされ、真空になったかのような一瞬の静寂のあと。
鼓膜を震わせる、純真で無垢な叫び声が、がんばれの四音が、ひとつの音になって場に響き渡った。
堀裕子は満足そうに微笑む。それから、大きな動作で、左手のマイクを口元へ、右手に握った先割れスプーンをヒーローへ。
「よーしっ、いきますよー! ムムムーン……、みんなの応援パワー、ヒーローに、とどけぇっ!」
堀裕子の声が響く。子供たちをハラハラさせるのに十分な間を置いて、ヒーローはゆっくりと立ち上がり、ヒーローのメインテーマがスピーカーから大音量で響いた。直後、さらにそのメインテーマをかき消すほどの、歓声。
「おおおっ!」
茜もまた、声をあげていた。両の拳を胸の前で握りしめている。
「ユッコちゃん、すごいです……!」
静かにそう漏らした茜の声色と表情からは、確かな闘志を感じた。
それから、ヒーローはシナリオ通りに悪役を退け、ショーは事故もなく終了となった。終了直後からのヒーローとの握手会で形成された長蛇の列もようやく短くなり、人でごった返していたイベントスペースは少しずつ落ち着きを取り戻していく。
「よろしくおねがいしまーす!」
茜はわずかに残った風船を配っている。こんなに必要なのかと思うほどに風船は大量に用意されていたが、あとは茜の手元にある数個で終わりだ。すぐに風船は最後のひとつとなり、茜の役割も終わった。
「おわりました!」
茜はすがすがしい顔でそう言った。俺は用意していたドリンクを茜に渡す。茜は目を丸くしていたが「ありがとうございます!」と言い一礼すると、ドリンクを受け取って口に運んだ。
そのときだった。
「ぁさん……」
かすれ声が聞こえたような気がして、俺は茜を見る。茜もまたこちらを見ていた。お互いがお互いの発した声だと勘違いしたようだ。その直後、同時に二人の視線は足元へ。
風船を持った小さな男の子が、俺と茜の服の裾をつまんでべそをかいていた。
「おかあさん……どこぉ?」
目に涙をためて、その子どもは茜にたずねる。
「……迷子か」
茜はすぐに子どもの前にしゃがみこみ、安心させるように頭を撫でてやっていた。
「どうしましょう、お母さんをさがしましょうか?」
「いや、こちらが動くとかえって混乱する。スタッフテントに連れて行って、ショッピングモール側の担当者に話してアナウンスを入れてもらおう」
「わかりました! じゃあぼく、お姉さんたちといっしょに行って、お母さんが来るまでいっしょに待っていましょう!」
茜がそう言って、子どもに微笑みかけたときだった。
子どもの手首に結ばれていた風船の紐がするりとほどけ、風船はヘリウムの浮力でそのままショッピングモールの天井へ向かってふわふわと浮きあがっていく。
それがスイッチになってしまった。
「うわあああぁぁぁぁぁん!」
子どもは声をあげて泣き出した。周りの人々もこちらに注目している。
「あちゃあ、風船が飛んで行ってしまいました……プロデューサー、余りは……」
俺は首を横に振る。風船は全て使い切り、あとは予備の紐くらいしか残っていない。
「うーん、残念でしたね……よしよし、元気出してくださーい」
「ああああぁぁぁぁん、うわあああああああ!」
茜は困り顔でなんとか子どもをあやそうとするが、子どもは泣きやまなかった。その場から動いてくれそうもなく、俺と茜が困っていたときだった。
「どうかしましたか?」
近づいてきたのはイベントを終えた堀裕子だった。
「ユッコちゃん!」
茜がぱっと顔を輝かせる。
「ひょっとして、お困りでしょうか!」
堀裕子もまた、子どもの前にしゃがみこんだ。子どもはいまだ声をあげて泣いている。
「お母さんとはぐれちゃったところに、この子の風船が飛んで行っちゃって……」
「なるほど!」堀裕子はしたり顔で大きくひとつ頷いた。「泣いた子どもをあやすなら、亜里沙さんか、このエスパーユッコ! お困りとあらば、このユッコにおまかせあれ!」
「どうしてそんなに自信満々なんだ……」
思わず漏れた俺のつぶやきは、堀裕子はもちろん、茜も聴いてはいない。
「取り出したるはこのスプーン!」
「おおっ、今度こそサイキックで曲げるんですか!」
「ふふふ、みていてください~」
堀裕子は茜に思わせぶりに笑いかけると、子どもの目のまえでスプーンをゆらゆらと揺らして見せる。子どもは興味をそそられたのか、泣き止むときょとんとした目でそのスプーンを見ていた。
「このハンカチを、こうして……あ、すいません、なにか紐みたいなもの、余ってませんか?」
「ああ、風船の紐の余りがあるぞ」
俺は余っていた紐を堀裕子に渡してやる。堀裕子は自分のハンカチでスプーンの柄の部分をくるみ、風船の紐をリボンのようにして結び、ハンカチを固定する。
「最後に、このペンで……」
堀裕子は懐から取り出した油性ペンで、スプーンの先の丸い部分に目、鼻、口を描く。ちょうど、スプーンの先を顔にした、てるてる坊主のような人形が出来上がった。
「これぞ! さいきっく・わらしべ人形です!」
「おおっ! それはどんなさいきっくなんですか!」
茜が興奮気味に堀裕子に尋ねる。子どもよりも興味津々だ。
「茜ちゃん、一緒にこの幸運の人形に、この子のお母さんが見つかるように、さいきっくぱわーを送りましょう! さあ、きみもいっしょに! いきますよ! ムムムーン!」
「ムムムーン!」
「む~ん!」
堀裕子と茜、それからさきほどまで泣きじゃくっていた子どもは、三人とも夢中になって人形に念を送っていた。
「よし! これできっと大丈夫です! さあ、お姉さんたちといっしょにテントにいって、お母さんを待ちましょう!」
堀裕子がそう言ったときだった。
「あ!」
子どもが茜の後ろのほうを指さして、顔をぱっと輝かせる。
「ああ! いた! もう、探したんだから!」
若い女性が駆け寄ってくる。この子どもの母親だろう。
「すいません、ご迷惑をおかけしました」
女性はこちらに向かって深々と頭を下げた。
「いえいえ、お気になさらず」
「そうです、人助けはエスパーの務め! 当然のことをしたまでです!」
「お母さんが見つかって、よかったですね!」
茜が子どもに微笑みかけると、子どもは嬉しそうに大きく頷いた。
「あら、そのお人形は……?」
母親が子どもの持っている堀裕子のスプーン人形に気づく。
「もらったの」
「すいません、あの、お返しを……」
「いえいえ!」堀裕子は母親を手のひらで制する。「これは私、エスパーユッコとここにいる茜ちゃん、そしてこの子の三人のぱわーが宿ったさいきっく・わらしべ人形! もしもどこかに困っていたり、悩んでいる人がいたら、この人形を渡してあげてください! きっと、さいきっくぱわーでその人のお悩みを解決してくれるでしょう! いまもさっそくこの子の悩みを解決してくれました!」
自信満々に言う堀裕子に、子どもの母親は思わず吹き出す。
「わかりました、それじゃあ……すいません、ありがたく頂戴します。ほら、お姉さんにありがとうって」
「ありがとう!」
すっかり笑顔になった子どもは、堀裕子と茜にそう言って、母親とともにその場を去って行った。
「ありがとう、助かった。ハンカチ、私物だったんだろ?」
俺が尋ねるが、堀裕子はさっき母親にしたのと同じように、俺に掌を向けて首を横に振る。
「気にしなくて大丈夫です! 今日はイベント、お疲れ様でした!」
「お疲れ様でした! ユッコちゃん、すごかったです! すごい人気でした!」
「あはは、あれはヒーローの人気ですから……でもいつか、あのくらいたくさんの人に囲まれて、ライブをしたいですね! ……それじゃ、着替えもありますし、私はこれで!」
言って、堀裕子はその場から去っていった。
茜はその後ろ姿をじっと見つめている。
まさか、堀裕子が超能力で子どもの母親を呼び寄せたと信じるわけではない。ただの偶然だろう。しかし、堀裕子の並々ならぬ自分の能力に対する自信は、堀裕子というアイドルを輝かせて見せていた。
「……すごいです。ステージから降りても、あんな風に人を笑顔にして……ユッコちゃんも、正義のヒーローみたいでした……私も、もっともっと頑張ります! プロデューサー、もっとお仕事やらせてくださいっ! ボンバーッ!」
茜は拳を天井に向かって突き上げ、気合を入れた。
「ああ。まだまだ下積みだが、着実にできることからだな。今日のイベントは事故もなく、無事に終了ってところだ。初仕事、お疲れ様」
俺が言うと、茜は目を丸くして、それからほんの少し頬を染めた。
「お疲れ様でした!」
言って、茜は勢いよく一礼した。
俺は茜の姿をみながら考える。俺も一歩ずつだ。茜たち五人が進むのと同じように。
復帰した先輩にこの五人を引き継ぐのがいつになるかはわからない。それまでは、できることを着実にやっていこう。ヒーローショーのシナリオと同じ、ありきたりでいい。ありふれた小さな仕事から順番に。きっとそれが最も正解に近い。
「よし、俺たちも撤収だ」
「はいっ!」
俺たちは心地よい疲労を抱えて、西日が射しこむイベント会場を後にした。
・・・END
――閉店後のショッピングモール。イベント会場の担当者は、缶コーヒーを飲みながら、イベントの終了報告をまとめていた。あがってきた書類を見て、驚いたように目を見開く。
「なんだ、この来店者数と売上……特売セールでもこんな数字見たことないぞ。今日だってべつに売れてるアイドルを呼んだでもないのに……誰かの念にでも呼び寄せられたのか?」
会場担当者のひとり言は誰にも聞かれなかった。その日の集客数が異常に多かった理由は、誰にも合理的な説明をつけることができず、ショッピングモールの伝説として語り継がれたという。