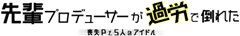
――上条春菜さんは、どういう経緯で今回のユニットに参加することになったんですか?
「私は、新しいユニットをやるから、と呼ばれて参加することになりました! プロダクションの偉い人のお眼鏡に叶ったってところでしょうか!」
言いながら、春菜は得意顔で眼鏡のテンプルをつまんでみせる。
「今回のユニットは、初めてアイドルとして活動する人もいて、活動期間も長めに取られていましたし、最初はいろんな不安があったんですけど、今はとっても楽しく活動しています! 一緒に活動したみんなもどんどん素敵になっていって、私自身もなんだか、すごく成長できたって実感していて、その……」春菜は少し恥ずかしそうにする。「とっても、いい仲間になれたって、思っています!」
――荒木比奈さんは、このユニットがアイドルとしてのデビューとなるそうですね。
「そうっス。周りはみんなアタシより年下っスけど、アイドルとしてはみんな先輩っスから、最初は肩身が狭いっていうんでしょうか、はやくしっかりしなくちゃって思ってたんスけど……すぐに、気にならなくなったっス。ってああ、もちろんテキトーにやるとかそういうことじゃないっスよ? 気負わず頑張ればいいって思えるようになったってことっス」
比奈はゆるく微笑む。その表情に緊張は感じられない。
――どうして、アイドルをやることになったんですか?
「えーと……この業界に興味はなかったんスけど、友達が勝手に応募したのがきっかけっス。えへへ、虚実入り混じってるっスけど、これ言ってみたかったんっスよね。そーいうことにしといてくださいっス。え、ダメ? あはは……引きこもってたところを、スカウトしてもらったッス。日向に出てきたからには頑張るっスよ」
――白菊ほたるさんは、この活動でなにか、得られたものはありましたか?
「得られたもの……ほんとうに、数え切れないくらいたくさん、大切なものをいただきました」ほたるは胸元でぎゅっと拳を握る。「これまでアイドルとして活動していて、いろんな大変なこと、辛いことがありました。けれど、手を差し伸べてくれる人達が、仲間たちがいて……きっと、これまでの辛いことはぜんぶ、これからのために必要なことだったんだって思えるようになったんです。辛いことが十あっても、幸せなことを百、ううん、もっともっと、私を支えて下さっているファンのみなさんに差し上げられたらいいなって、いまは思っています」
――あっ!? ……すいません、機材のトラブルが発生していて、撮れてなかったみたいです……
「ああ、やっぱり……すいません、こちらこそ……でも、大丈夫です。もう一度、お願いします」
そう言って、ほたるは微笑んだ。
――関裕美さんは、最初、このユニットに参加することになったとき、どう感じましたか?
「最初は、不安だった……知らない人と関わるのも苦手だし、人前に出ないお仕事のほうがやりたいって思っていたから。きっと、スタッフさんやメンバーのみんなにも、幻滅されちゃうだろうって、思ってた」
裕美は昔を懐かしむみたいに、空中を見つめていた。
「今は、あの時はどうしてあんなに不安に思ってたんだろうって、不思議に思ってるの。ううん、いまでも不安に思うことはたくさんあるけど……ええと、不安でも、大丈夫って思えるようになったのかな。不安なことは悪いことじゃなくて、できるようになる一歩前なんだって。それに、支えてくれる人達もいっぱいいるし、頑張れる……頑張らなきゃ、頑張りたいって思えるようになった、かな」
裕美ははにかむ。
「このユニットをやれてよかったって思ってる。だから、応援してくれる皆にもその気持ちが届くといいな」
――日野茜さんは、
「はいっ!」
――おおっと、すごく元気ですね。日野茜さんもこのユニットがアイドルとしてのデビューになるそうですね。なにがデビューのきっかけだったんですか?
「私も、スカウトしていただきました! 最初に声をかけてもらったときは驚いて、逃げ出してしまいました。家に帰って、落ち着いて考えたら、ちょっとやってみたいなって思って、それで参加してみることにしたんです! それからは毎日が楽しくって、きらきらしていて! レッスンも、お仕事も、ぜんぶ初めてのことばっかりで、とっても充実していました!」
――ユニットのみなさんとはどうですか?
「とっても素敵な仲間に巡りあえました! 本当に感謝しています!」茜は姿勢を正し、凛とした表情で答えた。それから表情を崩す。「ユニットのみんなも、それからプロダクションのみんなも、本当に友達がたくさん増えて、毎日が楽しいんです! そんな私の、私たちの楽しい、嬉しいっていう気持ちを、みなさんに届けられたらいいなと思っています! 新曲、応援、よろしくおねがいします!」
「はあーっ、緊張しました!」
茜はスタジオから出ると、ほっと胸をなでおろす。先に撮影を終えた比奈たちが茜をねぎらった。
「よし、ばたばたしてすまないが、次はストアイベントだ、表のマイクロバスに乗ってくれ」
俺は時計を見ながら五人に指示をする。
今日はついに、五人のユニットの曲が発売される日だった。
収録は概ね順調に終わり、事前の告知でも反応は上々。先輩のアシスタントをしていた時期の経験からすれば、準備しただけの成果が出ている、といったところだろう。
今日は複数の店舗でサイン会、そのうち一つではインストアライブ。ライブはネット配信も行われる。今は配信のための映像素材としてメンバーのコメントを収録していたところだった。
「それじゃ、ありがとうございました、あとはよろしくおねがいします!」
残っているスタッフに挨拶をして、俺もスタジオを飛び出す。
「みんな忘れ物ないな? よし、すんません、出発してください」
俺はマイクロバスの助手席に乗り込むと、ドライバーに言いながら扉を閉めた。
マイクロバスが走り出す。
「いやー、忙しすぎてこれからライブって実感がないっスね……本番、大丈夫でしょーか」
「サマーフェスのときみたいに大きな会場というわけじゃないですから、お客さんとの距離も近いですし」
「近いほうが逆に緊張しそうっス……」
春菜と比奈が談笑している。その後ろの席では茜とほたるが真剣な眼で歌詞カードを見つめていて、さらに隣の席では裕美が刷り上がったCDを手に取り、感慨深そうな目で見つめていた。
「はい、今日はこちらの五人に来ていただいています、美城プロダクションの新しいアイドルユニットの皆さんです! 本日ユニットソングがリリースということで、記念すべきレコ発、インストアライブ! ということになりましたー! 聴いたところによると、本当に今日までユニット名も秘密だったんですって?」
インストアライブ会場。司会の女性にマイクを向けられ、春菜が困ったように笑う。
「あはは、ええと、ちょっと成り行きみたいな感じなんですけど、私たちのユニット名、なかなか決まらなくて……ギリギリでようやく、メンバーのみんなでこれしかないねって言って決まったんですけど、いろんなところで未定って言っちゃったから、もうこうなったら発売日まで秘密にしておこう! ってことになったんです」
「なるほど! それなら、せっかくですからユニット名も、私からお伝えするより、みなさんから発表していただいたほうがいいですよね! それでは、さっそく曲からいっちゃいましょうか! 歌っていただきましょう! お願いします!」
「はい!」
五人はそろって椅子から立ち上がり、ステージに立つ。
茜がマイクを握る。
「ユニットが結成されてから、色んなことがありました! 楽しいこと、大変だったこと、ぜんぶ、この五人で分かち合ってきました! この五人だからできたこと、乗り越えられたこと、たくさん、たくさんあります! 私たちの曲を、どうぞ、聴いてください! 私たちは!」
茜は、大きく息を吸い込む。
「お客さん、みんな楽しそうにしてくれてたね」
移動するマイクロバスの中、裕美は嬉しそうに微笑んだ。
「本当に。でも、緊張しました……無事に終わって、良かったです」
ほたるがほっと息をつき、ペットボトルの水を口にする。
「ここからはサイン会だ。次の会場でイベント開始前に軽食が取れるから、腹が減ってるだろうがもう少し辛抱してくれ」
俺が言うと、はーい、と五人の返事が返ってくる。
「茜ちゃんのMC、ハキハキしててすごくよかったっスよ」
「そうですか? ありがとうございます」
比奈が褒めると、茜は恥ずかしそうに頭を掻いた。
「でも、なんだか……『五人』って言うのがちょっと変な感じでした。ずっと、プロデューサーさんも……プロデューサーさんだけじゃなくて、今日のドライバーさんもそうですし、トレーナーさん、スタッフさん、プロダクションのアイドルの皆……いろんな人たちに支えられてきましたから、五人って言ったけど、もっとたくさんだなって」
「私もデビューしたての時に、同じことを思いました」春菜が会話に入る。「ふだん私たちが観ていたアイドルの姿は、ほんとうにたくさんの人の手で支えられてるんだって」
比奈が大きく頷く。
「漫画も、原作と作画で分かれたりしますし、仮に一人で両方やってても、本にしてくれる印刷所さんや、読んでくれる人が居ないと成り立たないっス。アタシたちアイドルも、アタシたちだけじゃなくてプロデューサー、スタッフさん、ファンの皆さん、みんなで物語を作ってるんスね」
「そう思ってくれてるだけで十分だ。裏方は裏方で、見えてなくたってプライドもってやってるからな」
助手席に座った俺は、前を見たまま言って、それから一瞬だけ、となりのドライバーに目を向け――目が合った。お互いに笑って頷き合い、また前を向く。
晴れた空が眩しかった。
シートに体重を預け、俺もペットボトルの水で喉を潤す。
ここまで、とにかくすべてが激動だった。
それでもなんとか、五人をCDデビューまで連れてくることができた。
肩の荷が下りた、とはさすがにまだ言えないが、ここまでこれたことに、充実感を感じるくらいは許されてもいいだろう。
比奈の言ったように、アイドルは一人ではできない。
同時に、プロデューサーも、一人ではできなかった。
茜も、比奈も、春菜も、裕美も、ほたるも、そして俺も。
たくさんの人々に支えられて、いまここに立っている。
自然と、俺は感謝していた。
先輩プロデューサーに。茜たち、ユニットの五人に。両親に。これまで関わってきたすべての人に、感謝したかった。
ゆっくり恩返しをしていこう。そう考えながら、俺はペットボトルをドリンクホルダーに戻す。
「よーっし! 次のお仕事もがんばりましょう!」
「おおーっ!」
茜が大きな声で言うと、比奈、春菜、裕美、ほたるがときの声をあげる。
マイクロバスは、次の目的地に向けて走っていった。
五人の活躍は、続いていく。
季節はめぐり、冬がやってきた。
年末のウィンターフェスで、五人のユニットとしての活動はピリオドを迎える。
ウィンターフェスの舞台袖で出番を待つ五人の顔には、それぞれにさわやかな充足感が見て取れた。
俺はそれを少し離れたところから眺める。
茜と比奈は、新曲リリースから今日まででいくつものステージを経験し、もう新人アイドルだった夏の頃のような緊張は見られない。
春菜、裕美、ほたるも、夏に比べて一段と魅力を増している。
その頼もしい姿を見ながら、ふと、俺は自分の心に寂しさのようなものが去来していることを自覚する。
「……どうしたんですか?」
声をかけられてとなりを見ると、千川ちひろさんが俺の顔を覗き込んで不思議そうにしていた。
「なんだか、昔を懐かしむような、そんな顔をしていましたよ?」
そう言って、ちひろさんは笑う。きっと、俺の思っていたことを判っているのだろう。
「このユニットの活動も、これで終わりと思うと……少し、寂しいですね」
「プロデューサーとしては初仕事でしたものね。親心みたいなものでしょうか? ……お疲れ様でした、プロデューサーさん」
「ありがとうございます」
「よくやってくれたよ、おつかれさま」壮年の社員がこちらに近づいてくる。「けれど、これからだ。これからも、彼女たちの道は続いていく。彼女たちの物語は終わりじゃない。けれど、プロデューサーの作った道があるからこそ、彼女たちは走り続けられるんだ。ここまで、ありがとう」
「はい」
俺は舞台袖の五人を見る。もうすぐ前の曲が終わり、五人の出番だ。
「さあ、送りだしてやってくれよ」
壮年社員に促され、俺は五人のところへ歩いていく。
「プロデューサー!」
茜がぱっと顔を輝かせた。
「ついにここまで来たな。俺からはもう何も言うことはない」そう言いながら、俺は心の内で五人に向けてありがとうを唱える。「全力で楽しんでこい」
俺が言うと、茜は右手を前に出し、そこに五人が手のひらを重ねる。
「全身全霊、全力でやりましょう! ファイヤー!」
「さすがにもう、リア充じゃないなんていえないっスね。やりきりましょー」
「今日の眼鏡は特別です! いつも特別ですけど、特別中の特別なんですよ!」
「この五人でやれてよかった! そう思うの、心から!」
「幸せです……本当に!」
舞台袖のスタッフが片手を挙げる。
「よし、時間だ。行ってこい!」
俺の声で、五人の手のひらはぐっと沈み。
「おおーっ!」
そして、高く掲げられた。
曲のイントロが始まる。スピーカーの音が胸を打つ。ステージのライトが明滅し、客席のライトは茜達の色になる。
そして、五人は茜の掛け声に乗って光の海、歓声の波の内、輝くステージへと飛び出していく。
俺はその姿を見つめていた。涙は流さない。きっと二度とは訪れないこの瞬間を、涙でぼかして観るなんて、勿体ないことをするわけには行かない。
俺は五人の一挙手一投足を、一生忘れないように瞼に焼き付けた。
そしてさらに季節はめぐり、また次の春がやってきた。
「おい、寝るな、起きろ、おい」
「んがっ……」
声をかけながら何度か肩を叩いて、俺のとなりで船を漕いでいた同僚はようやく目を覚ました。
午後一番、どうしても集中力に欠け眠くなるのは、理解はできる。というか、身に覚えがある。
眠たげに目をこする同僚に、俺は自分の過去の姿を重ねて苦笑いした。
俺はプロダクションの全体会議に出席していた。
美城プロダクションの社内は新しいセメスターを目前に迎え、にわかに騒がしくなっている。
いくつかの新企画、人事異動が発表され、いまはどうにも表情の読みづらい社員がかなり大規模な新プロジェクトについての発表をしていた。
それからもいくつかの発表、連絡が続き、最後に役員から檄が飛び、会議は終了した。
俺は配布された資料をクリアファイルにまとめると、人事異動で新たにプロデューサーになった同僚と、その同僚にドリンクを渡している千川ちひろさんを見て、微笑ましく思いながら大会議室を後にした。
プロデューサールームに戻った俺は、デスクに置いてあるデジタルフォトフレームの電源を入れると、コーヒーを一口飲んで、パソコンの画面に向き合う。
茜、比奈、春菜、裕美、ほたるの五人は、それぞれの新しい道を歩んでいる。
比奈と春菜は、川島瑞樹らとの新しいユニットでの活動を始めた。瑞樹が多忙なため、なかなか全員が揃うことがないようだが、ユニットとしてはうまく回っているらしい。
裕美とほたるも、新たなメンバーと次のステップへと進んだ。先日の仕事で同じ現場になったときには、驚くほど成長した姿を見せてもらった。出会った頃に感じた危うさは、二人からはもう感じられなかった。
そして、茜は。
「おはようございますっ!」
プロデューサールームの扉が開き、元気な声が飛び込んでくる。
トレードマークの赤いポロシャツを着ている、見慣れた姿の茜だった。
「おはよう、相変わらず早いな」
俺は茜に声をかける。茜は「はいっ」といつものように元気に言うと、応接用のチェアに座る。
「茜、連絡してあった今日のスケジュールだが、ひとつ変更がある」
「え? そうなんですか?」
茜は意外そうにこちらを見る。
「ふふ」
俺はめいっぱい期待させるように意味深に笑ってみせてから、パソコンを操作する。プリンターが動いて、A4サイズの紙を一枚吐きだした。
俺はそれを取り、茜に向かって突き出してやる。
「おめでとう。この前受けてた、怪獣映画のヒロインのオーディション、通ったぞ」
茜は俺の突き出した書類を見て。
俺の目を見て。
もう一度書類を見つめ、それから顔をぱっと輝かせた。
「ほんとうですか!」
「ああ。今朝にオーディション通過の連絡が来た。ってことで、この打ち合わせを入れた新しいスケジュールがこれだ」俺は茜に変更されたスケジュールのプリントアウトを渡した。「これから忙しくなるぞ。覚悟しておけよ」
「はいっ!」茜の瞳に、炎のような闘志が灯る。「ううー、燃えてきました! ちょっと、気合を入れるために走り込みを!」
「これから仕事だ、我慢しろ」
言って、俺は笑う。
「次の夏のフェスにもソロの出番がある。かなりのハードなスケジュールだが、体調には十分気をつけろよ。俺もできるだけサポートする」
「頑張りますっ! やりますよっ!」茜は腰を落とし、両手を握り締めて、それから天を衝くように拳を突き上げる。「ボンバーーーーッ!」
プロデューサールームに、窓が割れるんじゃないかと思うほどの元気な声が響いた。
茜もまた、新しい道を全力で突き進んでいる。
日野茜。
荒木比奈。
上条春菜。
関裕美。
白菊ほたる。
彼女たちの活躍は、これからも続いていく。
一つの物語が終わっても、また次の物語へ。
アイドルたちは、これからも力強く、輝いていく。
・・・END